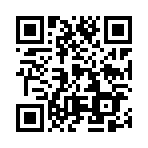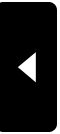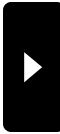2011年06月20日
復興基本法成立へ!
復興基本法成立=20日 東京都
東日本大震災からの復興の理念や体制を定める復興基本法案が本日参議院でやっと賛成多数で成立した。
そもそも政府の法案の提出が5月13日で震災から2か月もたっており、中身も実効性の乏しい内容であった。
公明党は復興施策の企画から実施までを一元的に担う「復興庁」の設置と、その財源としての「復興債」の発行、さらに復興施策を進める具体的な手法として「復興特区」の創設を提案したが、修正された法案は全て盛り込まれた。
さらに復興の基本理念には「一人一人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにする」「共生社会の実現」「女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき」などの表現が盛り込まれ、公明党がめざす「人間の復興」の考え方が反映された。
これから復興のスピードを一段と加速させ、具体的な施策を進めていかねばならない。
2011年06月19日
隠岐島前3島の西ノ島へ!町長との懇談・意見交換
西ノ島町升谷町長=19日 島根県
海士町の菱浦港から内航船いそかぜに乗り、西ノ島へ。
西ノ島町(にしのしまちょう)は島根県隠岐郡の町。
隠岐諸島の西ノ島に所在する。面積55.97平方キロメートル、人口3,125人(2011年3月現在)。
隠岐郡内では隠岐の島町に次ぐ2番目に大きな町である。
升谷町長・濱田副町長と懇談。篠原松江市議が同席。
離島の課題・要望を伺う。
・離島航路が高い。改善を強く要望される
・漂流漂着物の処理大変。予算300万 全然足りない。国の支援を。
・医療(島前病院が島にある)・介護の福祉は重点的取組みをすているが、さらに充実を
・情報格差の解消。本年度事業で光ケーブルの情報インフラ整備に4億円
・観光業は年間4万人と依然と比較し大幅減少
Iターンが約100人の内、4割が漁業。若い人達が住みやすい町づくりに挑戦されている。
別府港からフェリーに約2時間10分乗り、島根県七類港へ。
2011年06月19日
海士町の島民の皆様に国政報告・懇談
国政報告=19日 島根県
海士町の住民の皆様と懇談・意見交換。
初めに国政報告。私の4年間の取組みと東日本大震災の対策・政局・さらに公明党の離島振興政策についてお話しする。
その後も皆様から質疑。要望など伺う。
一番強い要望は、離島航路の料金が高いので半額位にしてほしい。(片道5600円)
医療・介護についても、離島故に負担がかかりサービスが受けれない等課題改善の要望など伺う。
日曜日にもかかわらず、熱いエールをおくっていただき、本当にありがたい。
海士町は中国地域で公明党の絶対得票率が一番高い位、皆さん真剣に行動されている。歓喜・元気の記念撮影。
2011年06月19日
海士町の地域再生への挑戦!教育の魅力で全国から人を呼ぶ
澤田副町長・岩本氏等=19日 島根県
隠岐の島西郷港からフェリーしらなみで海士(あま)町菱浦港へ。1時間10分程の距離。
海士町は(あまちょう)は島根県隠岐郡の町。隠岐諸島の島前三島のひとつ・中ノ島に位置する。面積33.5平方キロ、世帯数1,100世帯、人口2,352人(2011年3月)。
隠岐島前は、島根県の北60キロ、日本海に浮かぶ隠岐諸島の中の 3つの島(西ノ島町、海士町、 知夫村)で、世界第一級の 景勝地である「摩天崖」や日本の名勝「赤壁」に加え、 後鳥羽上皇や後醍醐天皇が配流された地としても有名。
海士町の澤田副町長・吉元高校魅力化PT担当課長・岩本高校魅力化プロデューサー等と懇談・意見交換。
離島が生き残るための様々な事例を伺う。特に”人づくり”からの”まちづくり”と教育に力を入れている取り組みに感銘。
以下海士町の『教育の魅力で全国から人を呼ぶ』の取組みを紹介。
【海士町の歴史】
・平成の合併でも3町村とも合併しない決断
・地方交付税の大幅削減で財源難
・自主的な給与の大幅カットを伴う行財政改革を断行。
「まちづくりの原点は人づくりにあり」という信念から少子化対策や次世代育成など投資。
【海士町の忍び寄る危機】
『高校の存続問題』
・島前高校10年間で生徒数半減(全校生90人程度)1学年1クラス
・10年間で入学者数77名(H9)から28人(H20)へ激減
・高校がないと経済的負担(3年間の本土高校に通わすと450万)
・島の活力もなくなり若者Uターンや出生数を増やす持続可能なまちづくりの島の方針も水泡に帰す
【対策】
①地域と学校の連携による魅力化プロジェクト
②指針1 学校連携型の公営塾「隠岐の國学習センター」(H22.4)
・一人一人の力を最大限に伸ばせる教育環境の整備
③指針2 「観光甲子園」グランプリ受賞(H21.8)
・地域の未来をつくる人材の育成
④指針3 「島留学制度」新設(H22.4)
・全国からも意欲ある生徒を募集(寮費食事補助)
【4年間の取組み成果】
・今春卒業生の3割が国公立大学合格(平成22年3月)
・入学志願者平成20年度27名から平成23年度44名(関東・関西からも)
【課題】
①課題1 教職員数の確保
標準法により離島など小規模校の場合、教員数8名。
8名では、高校の運営が出来ないため、県からの加算と町から4人の派遣で対応(社会教育主事、魅力化事務局、図書館スタッフ、事務スタッフ)
②課題2 継続性の担保とそのための仕組み作り
・島前高校管理職は2~3年おきに変わる
【今後魅力化の先に】
・若者の定住と持続可能なまちづくり
【要望事項】
離島の地理的条件に配慮した小規模校への教職員定数の充実『標準法の見直し』について
・「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下標準法)」は全国一律の基準で算定されている。昭和36年に本土の高等学校を想定して設計されており、離島の高校に考慮されていない。
・離島小規模校において
①本土並みの選択科目開設に必要な教職員配置
②養護教諭の配置③習熟度別指導教員の配置④進路指導担当の配置
⑤図書館司書の配置⑥実習助手の配置⑦寄宿舎舎監定数の加算などが盛り込まれ、離島地域の実情に適応した標準法の改正を
・もしくは標準法改正が難しければ、離島振興法の特例措置で対応。
(参考)
*島での就職や起業、島暮らしの運動を展開した結果
・188世帯310人のIターン者が海士町に定住(H23.3)
・Uターン者173名
*町の支援策
・Iターンのための定住対策(H16年度~H21年度)
定住住宅の新築39戸、空き家リニューアル28戸 合計67戸整備(H21)
・少子化対策
結婚祝い金(10万円)、出産祝い金、妊婦出産交通費助成、不妊治療のための交通費助成、18歳以下の精密検査のための交通費助成、保育料第3子以降無料、就学前児童奨励金5万円、頑張る子ども応援事業補助金など
2011年06月18日
隠岐の島視察・日本海離島の課題・要望を伺う
漂流漂着物視察=18日 島根県
早朝羽田空港から島根県出雲空港へ。出発時、梅雨前線の影響で出雲空港が視界不良のため羽田空港に引き返すこともあるとの事だったが、無事到着。
三島島根県代表と共に松江市内を挨拶まわりの後、鳥取県境港から高速船レインボーで隠岐の島西郷港に。隠岐の島で行われるウルトラマラソン参加の方々で満席。
篠原松江市議も合流し、隠岐の島内をまわる。素晴らしい自然の感嘆。
隠岐の島町は(おきのしまちょう)は、島根県隠岐郡の町で、2004年の合併によって隠岐諸島の島後(どうご)全域を占めるようになった。人口15,399人(2011年3月現在)
今回3回目の訪問。隠岐の島町の原田町長・門脇副町長等と懇談。下記課題・要望内容。公明党の離島支援の取組みにエール
・離島航路が高い(鉄道の2倍の料金。高速船5600円)離島航路の補助制度の抜本改革を推進してほしい
・医療の課題
医師不足(泌尿器科・神経内科)産婦人科もやっと2名常駐体制に
看護師不足も。
・介護(特養待機者70名近く)
・漂流漂着物(海外から流れる漂着物の対応町では困難)
1200万の支援ではまったくだめ。
・竹島問題など等
公明党の離島支援の取組みにエールをいただく。
早速、漂流漂着物の現場。長尾田港を視察する。
日本海の海岸に漂流漂着物が大量に流れ着き、その処理で本当に大変。住民のボランティアだけでは対応できない。国としての支援が必要。
2011年06月17日
東日本大震災の復旧復興対策へ!ヒアリング・意見交換
放射線による健康への影響に関するPT=17日 東京都
午前中参議院本会議にて障害者虐待防止法が全会一致で成立。公明党の長年の取組みが実り、嬉しい。
東日本大震災対策本部農林水産業対策チーム会議にて全国漁業協同組合連合会(JF全漁連)から震災対策(第2次補正予算)の要望を伺う。
1.各地域の実情を踏まえた漁業生産の復興・再生
2.生産から加工・流通の一体的な復興・再生
3.復興の担い手となるJF(漁協)の復興・再生
4.生産・生活の場としての漁村地域の復興・再生
・地域の実情を踏まえた町づくり、漁村・地域の復興
午後からは、第3回放射線による健康への影響に関するPTが開催され、「健康モニタリング体制の整備について」各省庁からヒアリング。意見交換を進めた。
2011年06月17日
再発性多発軟骨炎 難病指定 早期に!21万の署名添え申し入れ
要望書を手渡す=17日 東京都
「再発性多発軟骨炎・患者支援の会」の永松勝利代表や患者らと共に厚労省大塚副大臣を訪ね、約21万人の署名簿を添え、同軟骨炎の難病指定を求める要望書を手渡す。
公明党から木庭幹事長・江田・秋野・渡辺議員が同席。
・再発性多発軟骨炎は、軟骨組織や多くの器官の結合組織に痛みを伴う炎症が見られる病気。病状としては耳が赤く腫れた後、目、のど、心臓、血管、腎臓などさまざまな部位で炎症を起こす。重度の場合は死に至るとされる。
・根本的な治療法がない為、多くの診療科を受診する必要があり、診療・治療に時間がかかり医療費が高い。1か月の治療費は2万~30万円かかる。
・治療薬はステロイドや免疫抑制剤を用いるが副作用が強く、病気の症状に加え激しい副作用で日常生活、仕事に大きな支障をきたす。
・2008年に当時の渡辺副大臣に要請。
その後、難治性疾患克服研究事業の研究奨励分野に採用され、本日同席された聖マリアンナ医科大 鈴木教授の研究班が239例の症例を集め治療方法など研究を進めている。
(要望事項)
①同軟骨炎を難治性疾患克服事業の対象疾患に認定し、原因や治療法の継続的な研究を進めるとともに、患者の医療費負担の軽減を図ること。
②全国各地において再発性多発性軟骨炎の専門医を育成すること。
今後、公明党としても対応を進め、難病全体の支援に取り組んでまいりたい。
【2008年11月の渡辺副大臣要請のブログ】
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/diary/2008/11/12_1015.html
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/actions/2008/11/13_1115.html
2011年06月16日
細川大臣へ要望!大島青松園官用船継続・離島の妊婦支援へ!
質問=16日 東京都
厚生労働委員会で一般質問が行われ質問に立つ。
大島青松園の官用船継続、離島の妊産婦支援、障害者虐待防止法について25分間質問。
大臣からは、大島青松園の官用船継続の答弁をいただくが、職員の新規補充については明言せず、今後入所自治会の方々と来週懇談し対応協議との事。
離島の妊婦支援についても、まだ課題は多いが、障壁を乗り越え、実現してまいりたい。
(下記質問項目)
Ⅰ.ハンセン病療養所の課題について
①大島青松園の官用船継続へ船舶職員の補充をすべきではないか。
ハンセン病療養所の大島青松園がある大島と高松を結ぶ官用船の船舶職員が定年を迎えており、昨年も質問をさせていただきました。その後、平成23年度の船舶の民間委託は見送られ、定年を延長し再任用ということで、継続して直営職員で運航が行われてまいりました。
しかし、今年度末でさらに1名の職員が定年を迎え、今年再任用された2名に対しても再々任用が難しい状況にあります。
技能・労務職員等の採用抑制を規定している昭和58年の閣議決定によって、新規採用が難しいため、人材の確保が困難になっております。
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の制定や、衆参両議院において全会一致で決議したハンセン病問題の決議では、「入所者の最後の一人まで、安心して在園できるよう国が責任を持つ」という考えが示されておりました。その理念から考えれば、この大島青松園の官用船は継続し、船舶職員を新たに補充すべきと考えますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
②ハンセン病療養所の介護・医療などについて、国が責任をもって対応せよ。
Ⅱ.子育て支援について
①離島の妊産婦への支援をどのように考えているのか。
次に、母体保護法の議論に関連して、離島などの条件不利地域の医療についてお伺いいたします。
離島の妊産婦への支援についてであります。
全国には有人離島が312あり、そのうち産婦人科医がいない島が17あります。離島に住民票がある方から推計すると、出生数は約5000人、産婦人科医のいない島で約1200人が生まれております。
外界離島の沖縄県北大東島では、年間4人~10人が那覇市で出産しており、沖縄本島から360㌔離れているため、片道4.5万円、往復9万円(島民割引後6万円)という交通費が大きな出費となっております。
また、先日、視察に伺いましたが、内海離島の愛媛県の上島町(弓削島・生名島)では年間 20人が生まれております。これまでは、フェリーで3分の対岸の広島県の因島病院で出産を行っておりましたが、産婦人科がなくなり、尾道市まで数千円をかけて行かなくてはならなくなりました。こうした状況に対応するため、上島町では、1回5,000円の交通費補助を町単独で行っております。
昨年11月の衆院予算委員会における遠山議員の質問に対して、当時の少子化担当である岡崎大臣は、この離島の妊産婦への支援について「検討をさせていただきます。」との答弁をされておりました。
平成22年1月に閣議決定された「子ども・子育てビジョン」には、「安心して妊娠・出産できるように」として「妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減」を示されております。
こうした点から考えると、離島の妊産婦への出産に係る経済的負担の軽減についても、ぜひ検討して頂きたいと考えますが、大臣の認識を伺いたいと思います。
②安心こども基金の24年度以降の継続についてどのように考えているのか。
Ⅲ.障害者虐待防止法について
①障害者虐待防止対策支援事業の実施状況はどのようなものか。
次に、障害者の虐待防止についてお聞きします。
公明党は、2005年3月にワーキングチームを立ち上げ、この障害者の虐待防止に取り組んでまいりました。途中、法案を提出してもなかなか日の目を見ないときがありましたが、このたび制定に向けて動き出したことは、大変に意義のあることと思います。今後は、深刻化する事態を放置することなく、実効性のあるものとなるよう、取り組んでいかなくてはならないと決意も新たにするところであります。
そこで、この障害者の虐待防止に関する施策について、厚生労働省にお伺いいたします。
平成22年度より、障害者虐待防止対策支援事業が実施されております。これは、障害者虐待の未然防止、早期発見などの支援を行うために、研修や相談体制の整備などの事業に対して各都道府県や市町村に補助を出しておりますが、この支援事業の実施状況について、ご報告いただきたいと思います。
②対応窓口の実効性をどのように確保するつもりか。
③障害者虐待防止に向けた大臣の決意を伺いたい。
2011年06月15日
震災復興特別委員会で論戦が展開
真剣な公明党議員=15日 東京都
午前中、参議院本会議・災害対策特別委員会が開催。
また東日本大震災復興特別委員会の一般質疑が行われ、公明党から秋野・横山両議員が登壇。菅政権を追及。
被災者支援へ建設的な提言がなされた。
明日、厚生労働委員会で一般質問(25分間)の予定。(下記内容)
1.原発作業員の労働環境の改善
2.障害者虐待防止法
3.産婦人科医師のいない離島支援について
4.ハンセン病療養所大島青松園の官用船継続について
夕方から質問レクなど準備を進める。
2011年06月14日
「離島振興へ・全力!」 離島振興対策本部 第7回会合
遠山対策本部長=14日 東京都
夕方 離島振興対策本部第7回会合を遠山対策本部長を中心に開催。
①産婦人科のいない離島の妊産婦支援について(厚労省)
②漂流漂着物対策について(環境省)
③離島視察報告(6・4~5) 山本
④今後の活動について
先日の瀬戸内海離島の視察報告についてお話しする。
上記の課題も含めて今後離島振興法改正へ向けて、全国離島の視察など対策を進めてまいりたい。
2011年06月14日
難病であるパーキンソン病患者・家族の方々の請願書
生活再建支援対策チーム会議=14日 東京都
午後、生活再建支援対策チーム会議で第2次補正等について協議。
「全国パーキンソン病友の会」一樋事務局長等が来訪。
「パーキンソン病患者・家族の治療療養生活の質的向上の総合対策を要する請願書」2,758筆の請願書。(下記内容)
1.パーキンソン病の原因究明と治療法研究の促進、根治治療の早期確立
2.施策に当事者の声の反映
3.難病患者の就労支援、在宅就労助成、処方薬価の低減化など。
難病の方々支援に全力で取組んでまいりたい。
2011年06月14日
「腎疾患総合対策の早期確立を要望する」請願
愛媛県腎臓病患者連絡協議会=14日 東京都
8時30分から厚生労働部会が開催され今国会提出法案についてヒアリング・意見交換を進めた。
午後、愛媛県腎臓病患者連絡協議会(愛腎会)の戸田理事(四国ブロック担当)・山田副会長・門屋青年部長が来訪。
「腎疾患総合対策の早期確立を要望する」請願(愛媛の1500名)をいただく。
透析患者約29万人。1年間に新たに透析を始めた人37,543人。死亡患者は27,729人で毎年約1万人増加している。
10年以上透析を続けている患者は73,263人。65歳以上の患者は50%を超え高齢化が進んでいる。
1.腎疾患の発症と重症化予防にむけた総合的な対策を進める。
2.介護が必要な透析患者が介護保険を利用できるように。
3.感染症による透析患者の死亡を減少させる対策を。
4.透析医療における医療従事者・透析患者に関わる福祉従事者の不足の解消。
5.移植医療の普及推進
6.大災害が発生しても対処できる人口透析提供体制の確立
以上の要望を伺う。しっかりとした支援を進めてまいりたい。
2011年06月13日
「幸せをよぶ夢いっぱいの展覧会 藤城清冶・自宅スタジオ展」
87歳 藤城清冶氏=13日 東京都
世界的に有名な影絵作家・藤城清冶氏の自宅スタジオ展に妻と長男で行く。
藤城清冶氏(87歳)は目黒区に自宅があり、同じ慶應大学の先輩。先日、目黒三田会の席上、自宅でスタジオ展を開催している事をお聞きし、本日伺う。
玄関にはふくろうとワライカワセミ・猫などお出迎えがあり、藤城ワールドの世界へ。
代表的な影絵の数々。中国広島の原爆ドーム・四国の足摺岬・室戸岬など幻想的に光と鮮やかな色彩に感動。本当に「幸せをよぶ夢いっぱいの展覧会」(写真撮影が許されていたので紹介)
また爆笑問題の大田光のはじめての小説「マボロシの鳥」の絵本化、原画40点も。完成が楽しみ。
本当に心が満たされ幸せの気分に。
会場には夜にもかかわらず大勢の人々が。今までに3万5千人以上の方々が訪れている。愛媛県松山でも、90歳のときに展覧会を開催されるとの話しもあり、藤城氏の益々のご長寿と健康を祈りたい。
2011年06月13日
復興基本法が参議院で質疑へ!竹谷議員が登壇
竹谷とし子議員=13日 東京都
午後から参議院 本会議が開催され、衆議院から送付されてきた復興基本法について趣旨説明・質疑が行われた。
公明党から竹谷参議院議員が颯爽と登壇。
義援金等の支給の遅れを指摘、早急な解決策を菅総理に求める。
さらに公明党が主張した復興基本法案の復興庁、復興特区が修正で反映された背景、内容に関して提案者に質問。
公明党石田衆議院議員が答弁に立つ
明日からいよいよ委員会での審議。いち早い成立が望まれる。
2011年06月12日
同郷の方々と交流!近畿愛媛県人会懇親会
挨拶=12日 大阪府
早朝の新幹線で大阪へ。
近畿愛媛県人会(渡部会長)総会・懇親会に参加。
松本令子副会長の開会の辞の後、来賓挨拶。
中村愛媛県知事の愛媛県の近況等の話しの後、国会議員として挨拶をさせていただく。
乾杯(大西前会長)の後、愛媛県出身の石川ひろたか参議院議員と共に、故郷の皆様と親しく交流を深める事となった。
途中、「えひめ産マグロの解体ショー」や「がんばろう日本!」東日本大震災応援クイズ大会などの催しが開催された。
近畿全域から愛媛県に縁のある方々が集まられ、懇談をさせていただき、本当にありがたい。同郷の皆様の思いをしっかりとした政策・政治にしてまいりたい。
2011年06月11日
若き血の大合唱!平成23年度目黒三田会総会・懇親会
吉村会長=11日 東京都
本日は目黒区内を挨拶まわり。
夕方から目黒三田会総会・懇親会に参加。
吉村善和目黒三田会会長挨拶。
鷲尾副会長から収支報告、活動報告の後、来賓の方々から挨拶。
井田慶應義塾常任理事から慶應大学の近況報告。
目黒にお住まいの影絵作家 藤城清治氏から貴重なお話しも。今目黒の自宅スタジオ展が開催中。(6月12日までだが、ご本人からはさらに延長もされるとの事)
87歳になられるが、今なお現役で活動されている姿に感銘を受ける。
阿部元会長乾杯の後、懇親会に。
慶應卒業のマンスール ウズベキスタン共和国書記官の挨拶。目黒区に大使館があり、大変流暢な日本語で挨拶。
7月11日には目黒三田会分科会として大使館訪問の予定。(大使館分科会担当・斉藤やすひろ常任幹事)
青木目黒区長から「東日本大震災における目黒区の活動」の報告や初参加の方々の紹介など、慶應同窓の方々と親しく交流を深める。
安川副会長の中締めの後、応援指導部の福田三丈大先輩の指揮で若き血。
全員の記念撮影と思い出に残る日になる。
2011年06月10日
会期末へ!予算委員会で集中審議
予算委員会質疑=10日 東京都
本日は、終日参議院予算委員会の集中審議が開催。
公明党から山本かなえ・横山信一の両名が質疑に立つ。
山本かなえ議員は避難者支援・原発・外交等で菅総理を糾弾。
横山議員は被災地の漁業・養殖などで建設的提言。両名とも被災者の目線での的確な質問となった。
一方菅総理の弱弱しい姿は末期現象。一刻の早い退陣を。
2011年06月09日
ひきこもり支援に全力!全国KHJ親の会の方々からの要望
ひきこもり親の会の方々=9日 東京都
NPO法人全国KHJ親の会代表 池田佳世(東東京楽の会代表世話人)・NPO法人KHJけやきの会 家族会 田口ゆきえ代表理事・中垣内先生(精神科医)など全国の役員の方々が事務所に来訪。
本日厚労省・内閣府へ要望活動をされ、要望書を持参される。
「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」推進の要望事項(下記内容)
①「ひきこもり枠」就労の設置など「ひきこもりに対する就労支援」事業の充実
②長期重篤者の生活機能障害に対する年金等福祉対応の充実
③アウトリーチ人材の育成・強化
④家族会活動・居場所活動への国からの助成と官民協同の推進
⑤ひきこもり支援センターの全ての都道府県・政令市における設置充実
⑥ひきこもり医療に対する診療報酬の設定、「ひきこもり外来」など医療対応の推進
⑦小中高生に対するメンタルヘルス教育などの心の健康政策の推進
⑧「障害者制度改革推進会議」へ引きこもり親の会からの参加
⑨長期重篤で生活機能に困難を有する者には既存の枠に囚われることなく柔軟に生存権の保障を。
意見交換を進める。ひきこもり支援に全力で取組む事をお約束する。
(今までのひきこもり支援のブログ)
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/cat52/cat113/
2011年06月09日
東京都原爆被害者団体協議会(東友会)の方々と懇談
東友会の方々と意見交換=9日 東京都
社団法人 東京都原爆被害者団体協議会(東友会) 飯田マリ子会長・大岩副会長などと懇談。下記要請を伺う。
1.現行法改正要求の立法化を直ちに検討すること。
2.原爆症認定問題を訴訟によらないで解決するため、「確認書」で合意された大臣との定期協議を早期に再開すること。
3.原爆症認定について、検討会の結論を待つことなく、「新しい審査の方針」の積極的認定の対象疾病に関し、「放射性起因性」の制限を削除すること。
4.福島原発の事故による放射線被害者に対する健康の管理と保持、及び医療に、国が責任を持つ措置を直ちにとること。
被災の記録を保存し、健康管理手帳を発行し、年1回以上の健康診断を行うこと等。
午後、「放射線による健康への影響に関するPT」(加藤座長)の初会合。
長谷川ILO駐日代表が「労働者の放射線防護・ILO条約」について講演。
意見交換を進めた。
2011年06月09日
介護現場の方々の声を政策に!100回目の質問
質問=9日 東京都
厚生労働委員会で介護保険法改正案で、50分間質問に立つ。
今回で100回目の質問。
当選後4年間で国会の様々な委員会で発言・質問した回数が大台を超えた。現場をまわり、制度の狭間でご苦労されている声を1つ1つ吸い上げ、質問に。これからも謙虚に学び研鑽をと思う。
下記質問項目。
1.震災関連の介護問題について
①介護認定を1年間延長することで実情と合わないケースが出るのではないか。
②グループホームの被災者も食費・居住費の補助対象とすべきではないか。
2.介護サービスの充実について
①小規模多機能型居宅介護の機能充実をどのように行うつもりか。
②定期巡回・随時対応型訪問介護看護の地方での確保策はどのようなものか。
③家族介護の支援についてどのように対応するつもりか。
3.たんの吸引について
①研修体制はどのようになっているのか。
②報酬上の対応はどのようになっているのか。
③事故が起きた場合の責任体制はどのようになっているのか。
④ホームヘルパーや介護福祉士などの専門性を高める努力が必要ではないか。
4.介護サービス情報の公表制度について
①介護サービス情報の公表制度の見直しで事業者負担はどのように軽減されるのか。
②調査員の活用をどのように考えているのか。
5.介護従事者の育成支援について
①介護福祉士の試験の見直しをどのような手順で進めるつもりか。
②福祉系高校の支援を拡充すべきではないか。
③介護職員の処遇改善を交付金で行うのか、それとも介護報酬の引き上げで行うのか。
④処遇改善は幅広い職種を対象にすべきではないか。
6.介護報酬の地域区分について
①地域区分の見直しをどのように行うつもりか。
②介護報酬の地域差に人件費だけでなく居住費も勘案すべきではないか。
7.今後の社会保障について
①介護保険料と国庫負担の関係を見直すことへの見解を伺いたい。
②介護報酬と診療報酬の同時改定にどのように臨むつも