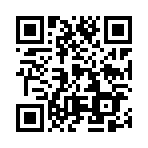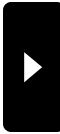2010年10月31日
第9回公明党高知県本部大会
あいさつ=31日 高知県
午後から第9回公明党高知県本部大会が開催された。
吉田機関紙推進委員長・黒岩幹事長と続く。
池脇県代表からの挨拶のあと、四国副議長としてあいさつ。
国政の状況、公明党の「社会保障トータルビジョン検討会」の進捗などお話しする。
最後は石田四国議長から国政報告。
明年の四万十町議選・統一地方選勝利への出陣と集いとなった。
2010年10月31日
ひきこもり支援の拡充を!高知「やいろ鳥の会」会長と意見交換
竹中会長と懇談=31日 高知県
全国ひきこもりKHJ親の会・高知県支部「やいろ鳥の会」の竹中あおい会長と懇談。
高知県黒岩県会議員・高木高知市議が同席。
ひきこもりの人は全国で数十万から100万人といわれ、平均年齢は30歳を超えている。
「やいろ鳥の会」の歴史、取組み・課題・要望を伺う。
2006年(平成18年)設立されたやいろの会。
翌年(2007年)からは、いの町に「いのポレポレ農園」を開設。
「家と社会の中間」「個と集団の中間」という意味での「中間施設」
として、社会参加、就労をめざしスタート。
毎月の勉強会や農園経営で家族同士のつながりや社会復帰の道を地道に取り組んできた。
平成21年4月からは、ひきこもりをめぐる悩みや情報を共有する「家族サロン」を火曜日に開設。家族が肩の荷下せる場所として活用されている。
また国の施策としての「ひきこもり地域支援センター」も四国で最初に開設。県立精神保健福祉センターで稼働している。
課題は
1.出てこれない人々への対応策(アウトリーチなど)
2.農園以外の中間施設・居場所づくりの確保(民間・NPO法人などとの連携)
3.親亡き後の生活・就労支援(年金、サービス支援、住居対策)など等。多くの壁がある。
これまでのひきこもり支援の取組みについて話す。11月予定の全国大会に参加する事や今後高知県・市との連携で支援を進める事を確認する。
(今までのひきこもり支援)
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/cat52/cat113/
2010年10月31日
認定こども園地方裁量型支援へ!高知市訪問
保育の課題・要望を伺う=31日 高知県
早朝、高松市を出発し高知県に移動。
市内にある認定こども園春野乳幼児園へ。
認定こども園地方裁量型連絡会会長でもある西岡園長と懇談。高木市会議員が同席。
まず豪雨による裏山の土砂崩れの現場へ。現状と対応策等伺う。
その後、政府が検討している「子ども・子育て新システム検討会」の議論の中で、地方裁量型認定こども園がどうなるのか?など等意見交換を進める。
高知市の地方裁量型認定こども園の保育所機能分として「ほのぼの保育事業援護費」の補助がさらに推進された事に対して、大変感謝される。
今後、全国の25園の地方裁量型認定こども園さらには認可外保育園など、未来を担う子ども達のために、不公平感がないよう対応する事を約束。
2010年10月30日
「無縁社会を変えろ!」独居高齢者の地域支援体制の取組み
新幹線から虹が=30日 東京都
台風のため、予定が変更となり午前中都内に。雨・風が強くなる中、午後の新幹線のぞみ号で岡山経由で香川県高松へ。新幹線から美しい虹が。
夜NHKで、「日本のこれから、無縁社会を変えろ!」との放映があった。
「一人暮らしの高齢者2010年465万人(2030年には717万人)・高齢者孤独死10年で5倍。」
「高齢者の近所づきあいがあいさつ程度、ほとんどないが57%など」
無縁社会の実態が語られる。
先日の厚労委員会で独居高齢者対策をとりあげたが、大変大事である。公助・共助をどう構築するか?早急な対策が求められる。
【下記委員会での質疑の議事録】
○山本博司君
続きまして、独居高齢者への地域支援体制の整備ということで質問をしたいと思います。
今年の夏に次々と明るみになりました高齢者の所在不明問題、このことによりまして、地域社会のつながりの希薄化、無縁社会、こういうようなことが今出ておりますけれども、急速な高齢化に制度が追い付いていかないと、こういう面があるわけでございます。この超高齢化社会にふさわしい仕組みを再構築しないといけない、このことがございます。
それで、最初に高齢者の置かれている状況に関しまして報告いただきたいと思います。
○大臣政務官(岡本充功君) 今委員御指摘の件につきましては、単身高齢者の世帯数の現状及び今後の推移ということだろうと思います。
国立社会保障・人口問題研究所によります二〇〇五年現在、高齢単身世帯数、これにつきましては約三百九十万世帯であり、十年後の二〇二五年には約六百七十万世帯まで増加するということが推計をされております。この日本の世帯数の将来推計によりますと、高齢者夫婦のみ世帯は二〇二五年は約五百九十万世帯というふうに推計をしているところでございます。
○山本博司君 これからやはりどんどん単身の高齢者が増える。多分、一番標準の世帯がこの単身の高齢者世帯といいますか、多くなってくると言われておりますけれども、こういう高齢者の方々が、やっぱり住民が安心をして暮らせる地域づくり、大変大事でございます。
これは、公的サービスだけでは解決できない課題に対応するために各自治体において地域福祉計画、これが策定が進められている状況でございます。ところが、この二〇〇九年の報告ですと、全国まだ五一・四%の自治体、約九百の自治体は作成をしていません。半分もされていない。熊本県は一〇〇%すべて策定をされています。最も低いのは鹿児島県の一四%。地域格差があるわけでございます。
こうした様々な今高齢者の問題ということがありまして、見守りの問題、様々な形を推進しないといけない。そういう意味で、厚労省は八月十三日に通知を出しまして、積極的な働きかけの強化を行っております。
そのアンケート等では、平成二十二年七月末現在の状況、策定が終わっているのか、策定予定であるのか、策定未定であるのか、策定が未定のところはどんな理由で策定ができていないのか、財源なのか、人の確保なのか。また、策定されているところは、例えばそれはどういう内容の見守りシステムとかネットワークを構築しているのかということを調査を依頼し、九月三日までにすべて上げよと、公表するからということで出しているわけですけれども、いまだ二か月たってもこの公表されておりません。一体こういう大事な問題に関してどのように考えてやるのか、このことをお示しいただきたいと思います。
○大臣政務官(岡本充功君) 委員御指摘の地域福祉計画というのは、まさに市町村がその地域の実情に応じた地域福祉の推進に自主的かつ積極的に取り組むために必要であろうというふうに、重要であろうというふうに考えております。
御指摘の数字、本年三月末現在で策定済みのところが四八・六、裏を返せば五一・四というのが策定できていないということでありますが、先ほどのお話のとおり、八月十三日に都道府県を通じて通知を出したところでありますが、その中で策定状況等の調査ということで、どういうふうな理由でできないのかというようなことも含めて市町村からの回答を今取りまとめているところであります。今月中の公表を目指しておりまして、またこの結果を踏まえて、この得られた情報からまた優良事例の抽出をして、そして順次厚生労働省のホームページでこういったものを紹介をしていきたいと。未策定の自治体等に課題解決になるような事例を紹介をしていくということが重要だと思っています。
先ほど、熊本と鹿児島の例を出されましたけれども、策定しているのはどちらかというと市の方が多くて、町村についてはその割合も低うございます。そういう意味では、その町村がなぜ割合が低く市の方が高いのかといったようなところもこういった調査から出てくるのかなというふうに思っているところであります。
○山本博司君 スピードを持って対応するということがやっぱり大事な行政の在り方ではないかと思いますので、この今月発表された後の対策も是非ともお願いをしたいと思います。
もう一点、地域包括支援センターということを質問したいと思います。
高齢者の孤立化とか虐待等の率の高い高齢者の早期発見をするためにこの地域包括支援センターの役割、これが大変重要になっております。約設置数が今四千で、サブも含めますと七千か所ございますけれども、この地域包括支援センターでは介護予防ケアマネジメントとか相談業務などを主に行っておりますけれども、ここに高齢者の情報を集約するとともに、支援センターの職員が戸別訪問をして高齢者の状況を把握するということを現実的に即した対応が一番身近に取っている状況でございます。先ほどの熊本の場合も、目標値、地域包括センターが今現状こういう見守りシステムが完備されているのが何か所で、いつまでにどうするかということを具体的に高齢者の把握をしております。
また、先日、私は和光市に行きました。七万人の市でございましたけれども、この孤立死ゼロ、これを目指しましてスクリーニング調査をずっとされておりまして、家庭訪問をして状況掌握をしているという例もございます。
こうした進んだ事例、全国展開をするためにも、こうした地域包括支援センターの予算がどうなっているのか、人員がどうなっているのか、十分じゃないのかどうか、そういうことも含めて拡充をするということが大事でございます。この地域包括支援センターの見守り活動の充実強化、この今後の取組に関してお伝えいただきたいと思います。
○大臣政務官(岡本充功君) 委員御指摘の地域包括支援センターが平成十八年に設置をされました。これは介護保険法の改正によって設置をされたわけでありますけれども、この地域包括支援センターがまさに今の見守り活動といったインフォーマルなアプローチでサービスを行うということは、大変重要だというふうに考えています。地域のネットワークづくりなどの調整役を担って見守り活動を実施をしていくということだろうと思っています。
平成二十三年度予算についてお尋ねがありました。
概算要求における地域包括支援センター、地域のコーディネートを担当する職員を配置して、見守り活動等の支援ネットワークの構築等を全国五十か所程度で実施するため、モデル事業の要求をしています。額としては五・五億円ということになっております。
さらに、二十三年度概算要求において、認知症高齢者の徘回に対応するため、地域包括支援センターなどを含め市民が幅広く参加をする、徘回高齢者の捜索、発見、通報、保護のためのネットワークづくりを進める事業を要求しているところでございまして、こちらにつきましては、今月の八日の閣議決定において円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策の中で、地域の日常的な支え合い活動の体制づくりということで、NPO法人、福祉サービス事業者等の協働による見守り活動チーム等の人材育成、地域資源を活用したネットワークの整備等に対する助成を行うというような書きぶりでお示しをしたところでございます。
また、地域包括支援センターが積極的に支援が実施できるよう、本年九月三日に、見守り活動等のネットワークを構築する際の個人情報の取扱いについて、その適切な取扱方法の例示を周知したところです。したがって、これまで個人情報保護法の枠があるからなかなかうまくいかないといったような声を聞いてまいりましたけれども、この例示を通じてそういった取組が進められるように厚生労働省としても後押しをしていきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、地域包括支援センターの機能強化を図り、地域の見守り活動を支援していく取組を推進していく、そのような考えでおります。
○山本博司君 これはなぜ特別枠なんですかね、五・五億。大事な予算ですよ。それを特別枠でコンテストに乗っけるみたいな形。違いますか。
○大臣政務官(岡本充功君) いわゆる補正予算の大要を今決めているところでありますけれども、先ほどお話をしましたのは徘回・見守りSOSネットワーク構築事業ということで、こちらの方が今少し前倒しを考えているということで御理解いただきたいと思います。
○山本博司君 続きまして、もう一つ、厚生労働省で、自公政権時代に、平成二十一年度から安心生活創造事業、これを三年間のモデル事業として今五十八の市区町村で実施をしております。これは、家族のサポートが期待できない独り暮らしの世帯などの見守り、買物支援であるとか、若しくは民生委員とか住民の活動とかサロンの集いの公的サービスに伴う見守りであるとか、居場所づくりと情報提供、こういうことを地域住民と連携をしてサポートをしております。
横浜市の栄区の公田町団地、これは高齢者の方々のお宅に、人感センサーを活用をして、十二時間以上で室内での動きがないとNPOスタッフがすぐ訪問をし、安否を確認するという、こういう見守りシステム、これが大きな効果を発揮していると言われております。
この安心生活創造事業の取組状況を御報告いただきたいと思います。
○大臣政務官(岡本充功君) 今御指摘がありました、少子高齢化社会における独り暮らしの高齢者等が住み慣れた地域において継続して暮らし続けることができる、生活を営むことができるようにするということは重要だろうというふうに考えています。
そういった中で、今御指摘のありました、民生委員やボランティア、民間事業者等が行政と連携して支援が必要な高齢者等の地域での生活を支える、そんな地域づくりのモデル事業として安心生活創造事業というのを全国今五十八の市区町村で実施をしています。
今委員から御指摘がありました横浜市の公田町団地、これはURの団地だと承知をしておりますけれども、こちらでは自治会や民生委員等がNPO法人等を設立し、見守りや買物支援を行う取組を行っておりますし、また、栃木県の大田原市では、自治会、民生委員、新聞配達員や郵便配達員等のネットワークを利用させていただいて見守りや安否確認を行う体制づくりを行っているというふうに承知をしておるところであります。
今後とも、国としましてこのような成果を取りまとめ、全国に発信をしていく。まさにこれはモデル事業でありますから、こういった取組を通じて厚生労働省としての対策、また対応を決めていくことになるんだろうというふうに考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。
やはりこの取組というのは大変大事な取組ですので、是非とも推進をしながら、今各省庁とも、例えば総務省もICTを使ってのこういう見守りネットワークシステムにお金が出て推進をするとかということもございますので、よく連携をしながら推進をしていただきたいと思います。
それで、最後になりますけれども、この問題の最後になりますけれども、公明党は九月二日に、この緊急経済対策の中で、地域における高齢者の見守りなどのネットワーク体制の整備のための独居高齢者支援体制整備モデル事業、この創設を主張しております。今お話がありました緊急通報システムとか配食サービスとか訪問活動、こういう見守り体制の整備には、公的機関のサービスだけではなくて住民などの地域のネットワークとか民間企業とかNPO法人などの地域の活力、これをやはり総合力で活用すべきでございます。
大臣にお伺いしますけれども、こうした面での税制面、金融面での優遇、こういうことがやっぱり必要であると思いますけれども、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 今委員が御指摘のとおり、この問題については大変大事なことで、私どもとしても積極的に取り組んでいきたいというふうに思っております。
そこで、この間の緊急総合経済対策、これにおきましてNPO法人、福祉サービス事業者等の協働による見守り活動チーム等の人材の育成、あるいは地域資源を活用したネットワークの整備等の助成、これの必要性ということがこの経済対策で掲げられました。これを踏まえまして、補正予算に百億円程度の予算を計上してしっかり対策を遂行していきたいというふうに思っておるところでございます。
2010年10月29日
自立する四国へ!地域経済活性化・「命の道」整備促進
愛媛県の首長の方々=29日 東京都
午後から政調全体会議。政府提出の補正予算概要について関係省庁からヒアリングし、意見交換を進める。あまりに遅すぎる対応。中身の吟味はこれから。
また愛媛県八幡浜市(大城市長)宇和島市(石橋市長)愛南町(清水市長)久万高原町(永井副町長)などが事務所に来訪。
21世紀・活力ある道づくりを目指す「四国連合協議会」として、四国の道路整備の改善を強く要望される。
【四国の道路整備が抱える現状と課題・要望】
①大幅に遅れている四国の道路整備
・全国平均より約16%の遅れ。
・四国における移動手段は約96%が自動車交通
②高規格道路網の「ミッシングリンク」
・四国8の字ネットワーク供用は未だ約6割
③急がれる「命の道」の確保
・今後30年以内に60%程度の確立で想定される南海地震の対応
④地域間格差の拡大を助長する「高速料金制度」
・四国へ行く場合、本州や九州の移動と比べ2~3倍の金額
夜は、全国みかん生産県議会議員の対策協議会意見交換会に参加。愛媛県の県議の皆様など交流を深めた。
2010年10月29日
中小企業・建設業の悲鳴を聞いて!政策要望の団体ヒアリング
日本建設業団体連合会などからヒアリング=29日 東京都
8時30分から厚生労働部会。国対役員会・本会議・災害対策特別委員会と続く。
さらに各団体から平成23年度の政策要望をお聞きする。
最初は、社団法人「日本建設業団体連合会」社団法人「建築業協会」社団法人「海外建設協会」の3団体。
日建連の竹村常務理事から挨拶の後、平成23年度税制改正要望として下記の内容。
建設業界は昨年度、日建連法人48社の受注総額31年ぶりに10兆円を下回り、極めて厳しい状況が続いている。
1.適切な経営環境を確保するための税制
①印紙税の廃止(印紙税)
②工事損失引当金の損金算入(法人税)
2.事業を促進するための税制
①都市・住宅対策促進税制
・特区制度の導入に際しての法人税、固定資産税等の減免措置
3.海外市場進出関連税制
①海外大規模インフラプロジェクトに関する準備金制度の創設(法人税、法人住民税)
続いて、日本商工会議所。山口代表の挨拶の後、宮崎常務理事から中小企業の活力強化、地域経済活性化に向けての政策要望を伺う。
【調査結果による中小・小規模企業の現状】
・408の商工会議所調査結果より、中小企業の景況感は、9月以降停滞感が一層強まっている。
・日銀短観と商工会議所調査の業況DIは20ポイントの差があり、緊迫感の把握が日銀、政府は遅い。(日銀短観は資本金2000万以上なので、小規模企業の実態反映がされていない。)
【政策要望】
1.円高対策(為替水準を90円台にもどすあらゆる手段を)
2.中小企業支援の拡充・強化(仕事を創る支援)
3.地域活性化対策の強化(社会資本整備の前倒しなど)
4.中小企業等関連税制の拡充・強化
(法人税・法人軽減税率引き下げ等)
5.地球温暖化問題および雇用・労働問題など。
建設業・中小企業の厳しい状況を伺い、早期の様々な政策実現が求められる。
2010年10月28日
海運が盛んな長崎県・大島造船所での命名式
FEDERAL YUKINA号=28日 長崎県
午前中、長崎県 大島において、新船の命名式に参加。
大島造船所にて新装となったFEDERAL YUKINA号。
3万5千トンの船。全長200㍍。雄大である。
命名式には大島島民の皆様も参加されていた。島の子供たちの歓迎太鼓の後、支綱切断や祝砲発砲などの命名式のセレモニーが行われた。
本船視察では、船内を見学。日頃見れない船の舵取りの心臓部など拝見する。
祝賀会では(株)大島造船所 堀社長代行やカナダのFEDNAV LIMITED President Mr.Paul M Pathy(社長)・八幡浜汽船(有)山本社長(長兄)などが挨拶し、懇親会。
最後は、大島造船所の2号岸壁からYUKINA号の出航を見送り、一連のイベントが終了。
海事議員連盟に所属する議員として、大勢の海事に関わる方々と交流を深める事となった。
特に、円高の影響で大変厳しい状況など伺う。経済政策など政治の役割が大事。
2010年10月27日
政策要望団体ヒアリング(日本司法書士連合会・政治連盟)
日本司法書士連合会・政治連盟からの政策要望=27日 東京都
国対役員会の後、災害特別委員会理事懇談会が開催され、奄美大島の災害状況の報告をうけ、今後の委員会等の日程など議論する。
また団体ヒアリングも行われ、日本司法書士会連合会・日本司法書士会政治連盟から政策要望等伺う。
日本司法書士政治連盟安井会長の挨拶の後、日本司法書士連合会 里村専務理事から平成23年度政策要望や平成23年税制改正要望の説明がある。
平成23年政策要望
1.司法制度改革関連(国民に身近な法律家としての司法書士改正)
①司法書士相談業務の確立
②司法書士自治に基づく懲戒制度の確立
③簡裁代理等の充実
④司法書士の整備
2.登記制度改革関連要望
①オンライン申請の利用促進・司法書士の権限と責任の強化
3.民法(再建法)改正関連要望など。
お伺いした内容について、公明党としてしっかり対応する事をお話しする。
2010年10月26日
「釧路市の生活保護自立支援事業の取組み」を視察
釧路市の取組みを伺う=26日 北海道
午後から、釧路市内へ。
釧路方式と呼ばれる「釧路市の生活保護自立支援プログラムの取組事例について」釧路市福祉部の方から説明を伺う。
渡辺参議院議員や地元戸田道議・5名の釧路市議が同行。
訪問の趣旨など渡辺議員とともに挨拶の後、釧路市の松浦副市長・藤原副議長より歓迎の挨拶。
櫛部生活支援主幹から釧路市の取組みについて説明をいただき、意見交換を進める。
1.釧路市の動向
*人口185,487人 世帯92,848世帯
*釧路の3大産業(水産・石炭・紙パルプ)の低迷
求人倍率 0.26(H21年)
2.釧路市の生活保護の動向
①保護世帯 5940世帯 保護率 49.5 保護人員9250人
市民20人に1人が生活保護。母子家庭16.3%と全国の倍
②保護開始世帯 886世帯 ・廃止世帯 521世帯
③保護開始理由 1位就労収入減 2位傷病(初めて収入減1位)
3.釧路市の自立支援事業の取組み
(1)母子世帯の自立支援モデル事業(平成16、17年)
・釧路公立大学との共同研究(客観的に把握し、ニーズをつかむ)
・ワーキンググループの委員会の立上げ
(2)自立支援プログラム事業(平成20、21年)
①中間的就労の場の確立。
・日常生活自立として「重度障がい者介助ボランティア・えぷろんおばさんの店」手伝い
・社会生活自立として11のプログラム(介護、公園清掃、障がい者作業所、動物園ボランティアなど)
・就労自立として5事業(インターンシップ事業・職業訓練機関など活用プログラムなど)
②貧困の連鎖を断ち切るための教育支援
高校生進学希望者学習支援(冬月荘)
(3)協同の相手(受け入れ事業個所 13か所)
・NPO法人地域生活支援ネットワークサロン、NPOおおぞらネットワーク、社会医療法人、財団法人 釧路公園緑化協会、NPO釧路市動物協会など。
(4)対象者
*対象者は生活保護受給者の原則18歳から64歳の未就労の参加希望者と中学生、高校生のうち参加希望者
(5)目的
・地域と一緒にありのままの自分を受け入れてもらえる場を生活保護受給の大人においては、中間的就労の中に、中学生・高校生においては、勉強会などの中に作る。
・参加する受給当事者自身がその中で自尊感情の回復を図り、其々にあった自立の一歩を踏みだす。
(6)利用者
平成18年度133名 平成19年度140名 平成20年度221名
平成21年度170名 平成22年度7月現在199名
(7)費用
セーフティネット支援対策等事業費補助金(年間約600万円)
(国の10分の10)
(8)課題・要望
①セーフティネット支援対策事業補助金がいつ終わるか不安のため、取り組まない自治体も多い。制度化が必要。
②ケースワーカー(CW)が13名不足しており、全国共通の課題。CWの増員を。
③地方負担が4分の一負担。財政的に厳しい現状。地方負担の見直しを。
その後、NPO法人地域生活ネットワークサロンが運営する地域企業創造センター「まじくる」とコミュニティハウス「冬月荘」を視察。
「まじくる」は仕事探しの相談やインターンシップ研修や仕事づくり起業など年間80人を研修。企業やNPOとのマッチングに尽力している。
コミュニティハウス「冬月荘」は、子どもの健全育成事業として、希望する生活保護受給中の中学生及びNPOが相談を受けた要保護世帯の中学生が対象で費用は無料。
チューターとして生活保護受給中の高校生、受給中の大人。大学生、NPO職員・ケースワーカーなど多彩なメンバー20名以上が対応。
勉強以外にもスイーツづくりなど自主活動などこども達の居場所としても活用されている。
子どもたち(参加者)の声として
「明るくなった」「ふれあう人が多くなった。」「大人と話せるようになった」「親に楽しさを話すようになった。(親とのコミュニケーションがとれるようになった)」
生活保護受給者のチューターの声
「外へ目がいくようになった」「目的がある」「うまく教えられるように絶えず頭の中で考えている」「いごごちがいい」
今まで社会との疎外感や否定されてきた自分から、役にたっているとの存在価値・生きる意欲が湧いてきた。など等
今回の視察は、大変貴重な釧路市の取組みで、参考になり感銘を受ける内容であった。今後の施策反映に努めたい。
2010年10月26日
日本最大の湿原「釧路湿原国立公園」を見学
広大な釧路湿原=26日 北海道
早朝の便で、北海道釧路空港へ。
渡辺参議院議員と「社会保障トータルビジョン検討会」の「貧困・格差チーム」として釧路市を訪問。
釧路市内に行く途中、釧路湿原国立公園へ立ち寄る。
釧路湿原(くしろしつげん)は、釧路平野に位置する日本最大の湿原である。面積18,290ha。
壮大な景観を有し、貴重な野生生物が分布する釧路湿原は、日本を代表する傑出した自然の風景地で国立公園に28番目に指定された。(昭和62年)
釧路短期大学 大西英一教授の案内で木道を歩く。地元月田市議・松橋市議も同行。
紅葉の木々や自然の様子・釧路湿原の歴史などを伺いながら進む。
釧路市湿原展望台から一望できる風景は絶景。その広大さにびっくり。
湿原には、特別天然記念物タンチョウをはじめとする各種鳥類のほかキタサンショウウオ等貴重な動物が生息している。
また、湿原の主要部は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)の登録湿地とされるなど国際的にも高く評価されている。
広大な原自然の光景にただ感動。
2010年10月25日
「求められる障がい者虐待防止法とは」院内集会
「求められる障がい者虐待防止法とは」院内集会=25日 東京都
予算委員会の集中審議が行われ、公明党から草川副代表が登板。経験に裏付けられた、メリハリのある質問に感銘を受ける。重みと貫禄が漂う。下記質問項目。
1.政治と金への対応
2.中国漁船衝突事件
3.政策コンテストはパフォーマンスでは?
4.中国企業の日本進出の現状について
夕方、日本弁護士連合会主催の「求められる障がい者虐待防止法とは~医療機関と学校における現状は放置できない~」の院内集会に参加し、挨拶。
虐待の場所として、家庭・施設・雇用先のほか、医療機関と学校現場があるが、与野党の法案に医療機関と学校が含まれていない。本日は医療機関や学校現場の実態を伺う。
高齢者虐待防止法、児童虐待防止法が制定されたが、まだ障がいのある人に対する虐待防止方はまだ。
本日の内容も含め、議員立法として、早期制定めざし、頑張ってまいりたい。
2010年10月24日
統一選大勝利へ!「公明党徳島県本部大会」が開催
県本部大会であいさつ=24日 徳島県
午後から公明党徳島県本部大会が徳島市で開催された。
明年の統一地方選勝利へ向けての出陣の大会となった。
長尾代表の後、党幹部として挨拶。石田四国議長・谷合参議院議員も出席。
質疑では、「こどもたちの命を守る予防接種行政・特にワクチンの公費助成・定期接種の公明党の取組みについて」答弁する。
統一地方選候補紹介・決意。
最後に勝鬨。雨の中、県内から集まられた大勢の支持者の皆様に感謝。
2010年10月24日
市場開放の「たかまつ市場フェスタ2010」
常設イベント会場にて=24日 香川県
午前中、たかまつ市場フェスタ2010に参加。
高松市民の台所、高松市中央卸売市場のイベント。
1日市場を開放して、日頃は体感できない、見る・触れる・買うの醍醐味の企画が満載。
メインステージでは、「模擬せり」がスタート。活気あふれるセリの模様が披露。その後模擬体験も。
水産物棟せり場では、「魚のつかみ取り」のコーナー。子どもたちが水槽内のはまちやたこをつかみ取り。また「マグロ解体ショー」の実演も。
常設イベントでは、野菜格安袋詰め放題・香川ブランドハマチ試食コーナーなど大喜びの企画も。
その他、「親子で食育・花育講座」として「フラワーアレンジメント教室・魚のさばき方教室」など開催され、大勢の市の方々が集われて、楽しまれていた。
市民が身近に青果や漁業市場を実感でき、大変有意義な企画である。
また市場関係者とも懇談。
・現在の農家や漁業者など生産現場での価格下落
・日本政府のTPPなどの政策による国内生産者の打撃など現政権の施策の一貫性のなさ等。
課題・要望もいただく。
2010年10月23日
大島青松園の官用船の民間委託反対!委員会質問にて
大島青松園=6月20日 香川県
午前中、都内の近隣まわり。緑道の花々に心が和む。
午後、品川駅から新幹線で、岡山へ。途中、雄大な富士山が。
岡山駅からマリンライナー号で瀬戸内海を渡り、香川県高松へ。
瀬戸内海の大島青松園。
国の隔離政策で離島に追いやられたハンセン病療養所の方々。今唯一の交通路の船問題で揺れている。
先日の厚生労働委員会で細川大臣に質問した。その内容の議事録を掲載したい。
参院厚生労働委員会 平成22年10月21日(木)
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。本日は、細川大臣の所信ということで質問をさせていただきます。
細川大臣は、四国の高知のいの町の出身ということで、私も四国ですので大変身近に感ずるわけでございます。座右の銘が、何か、「嵐しは強い木をつくる」嵐しがお好きのようでございますけれども、しっかりこの厚生労働行政、幅広い行政でございますから、リーダーシップを発揮されて推進をお願いをしたいと思います。
それでは、今日私は、新卒者の就職支援、また独居老人の方々への支援策、またうつ病対策という観点で質問をさせていただきます。
ただ、その本題に入る前に、一つハンセン病支援について質問を申し上げたいと思う次第でございます。
現在、十三のハンセン病の療養所で約二千四百名の方々が入所をされていらっしゃいます。平均年齢はもう八十歳を超えておられます。私も今まで、岡山県の長島愛生園とか邑久光明園、また東京都の多磨全生園、そして今、地元香川の大島青松園等も訪問しまして、入所自治会の方々の声も聞きながら、当委員会でも何度も質問をさせていただいた次第でございます。
この五月二十五日の質問では、ハンセン病問題の基本法、この制定を受けまして、各今十三の療養所では将来構想に基づき、地域開放ということで進めていらっしゃいます。多磨全生園の保育園の問題を取り上げさせていただきました。この多磨全生園、また熊本の菊池恵楓園の地域開放の進捗状況、まずこの点を報告をいただきたいと思います。
○大臣政務官(岡本充功君) 今御指摘、御質問のありました多磨全生園などの地域開放の進捗状況ということでお答えをしたいと思います。
国立ハンセン病療養所の地域開放については、ハンセン病問題解決促進法において、入所者が地域から孤立することがないよう、療養所の土地等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することが可能となったところであります。これは平成二十一年四月一日施行であります。
国立療養所多磨全生園におきましては、施設内の土地を保育所として利用するための準備を今進めております。今後、公募の実施、また利用者の選定等の手続を行い、二十四年四月を目途に開所が可能となるようにしていきたいと思っておりますが、また、国立療養所菊池恵楓園についても、多磨全生園と同様、保育所利用のための計画を進めているところでございます。
いずれにしましても、今後とも入所者や施設管理者等の意見をよく聞いた上で、各施設の地域開放に向けた取組を進めていきたいと思っております。
○山本博司君 やっぱりハンセン病の患者の方々、子供を持つことが許されなかった、そういう患者の方々の皆さん方が、その敷地内で子供の声が響き合っていく環境が実現できるということは本当に歴史的に画期的だというような声もあるわけでございます。こういう、各今十三の療養所ではこういう将来構想を推進されております。
もう一つ、私の地元の香川県大島青松園のことを取り上げさせていただきたいと思います。この大島青松園は、十三ある療養所の中で沖縄、奄美を除きまして唯一離島でございます。大島と高松を結ぶ約八キロ、この唯一の足がこの船でございまして、官用船ということで二隻運航がされていらっしゃいます。私も何度も乗せていただきながら、その場所にも行かさせていただきました。今六名の船員がいらっしゃいますけれども、うち二名が今年度退職をされるということで、厚労省は補充をしないで、二〇一一年の概算要求では一隻を民間委託すると、このようなことを決定されたという報道がございました。
その点で、大島青松園の入所者の方々、大変不安が広がっております。夜間の緊急時に今までのように対応してもらえるのだろうかと、また便数が減るのではないか、そういう不安が募っておりますし、ハンセン病の療養所の方々は、そういう国の隔離政策によってその島に追いやられてしまったわけでございます。
そういう一つしかない交通手段という意味で国の責任の棚上げではないか、様々な強い反対をされておりますけれども、この点どうお考えでしょうか。
○大臣政務官(岡本充功君) 御指摘になられました国立療養所大島青松園においては、平成二十二年度末に二名の船員職員が定年退職の予定であるというのは事実でございます。この職員の退職に伴い、いわゆる官用船二隻の運航が難しくなるのではないかと、こういった御指摘であると思います。御指摘のとおり、一隻を民間に業務委託して運航に支障がないように継続をしていきたいというふうに考えております。御希望とはいえ、残念なことでありますけれども、国家公務員、来年度の新規採用抑制が大変厳しいという状況で、この方針の下、新規に船員を採用するのは極めて困難でございます。そういった事情も是非御理解をいただき、今後入所者の皆様方と、増便を含めた利便性の向上や夜間や救急に対する対応等全体的にサービスの向上を努めて、御理解をいただいていきたいというふうに考えております。
直営と業務委託との両輪によって入所者の方々の安全確保と利便性の向上を図っていくということは重要なことだと考えておりますので、御理解がいただけますようにお願いをしたいと思っております。
○山本博司君 これは本当にもう国の勝手なそういう形の内容であるというふうに多くの方はおっしゃっていらっしゃるわけでございます。やはり最後の一人まで国が責任を持つと、このように言ってきたわけでございまして、医療の問題、また唯一、交通手段が一つであるこの船の問題というのは大きな問題でございます。
特に大島青松園の場合は、将来構想ということで、今香川県とか広島県とか岡山県とか多くの離島を持っております、こうした離島医療を支援をする瀬戸内海離島医療センターという構想もありまして、この二隻の船を活用しながら、その将来構想をやりながらやっていきたいという思いもあるわけでございまして、この十月十四日には、香川県の自民、民主、それから公明、社民、共産、すべての全会派がこのことに関しまして全会一致で反対の決議をし、大臣にそのことを申し入れるという形でございます。このハンセン病問題の基本法の趣旨に反しているのではないかというふうな形で強い懸念を示されているわけでございます。
大臣にお聞きをしたいわけですけれども、やはりこういう問題というのは、現場の皮膚感覚というのがすごく大事だと思います。前回の委員会でも長妻大臣に、入所先に行ったことがございますか、同じ、民主党政権になって政務官以上の方が行ったことがあるんでしょうかと、こういう話をしましたら、まだ一度もそういうところに行ったことはないということでもございました。大臣は行かれたことがあるんでしょうか。また、この問題をどう思われますでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) まだ私も現場に訪問したことはございません。したがって、今委員のいろんなお話も聞きまして、この問題にはしっかり対応していきたいと、いずれ時間を取りまして訪問もしてみたいというふうに思っております。
○山本博司君 是非とも、やはり国のこういう隔離政策でハンセンの方々がもう大変な思いをされていらっしゃるという、現場も含めて、その状況の中でこの船がどういう意味があるのかということもやっぱり実感をされた上でのそういう判断をしていただきたいと思う次第でございます。
全国の十三のハンセン病療養所の方々は全国を挙げて大島のこの船の問題は単なる一療養所の問題ではないと、そういう人権の問題だということもおっしゃっておられるわけでございますので、大臣は人権派弁護士であったわけでございますので、同じ四国でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
2010年10月22日
障がい者就労支援に取り組む「フードコミュニティ目黒」
フードコミュニティ目黒=22日 東京都
目黒区のNPO法人フードコミュニティ目黒(FC目黒)のお披露目・懇親会に参加。
FC目黒は、知的障がい者の自立や社会参加促進のため、渥美理事長が2006年12月設立。
おこあ等の美味しい弁当をつくられている。現在13人の障がい者が生き生きと働いている。渥美理事長など関係者の皆様のご苦労に感謝である。
お披露目会は、渥美理事長からの御礼のあいさつ。
行政側から青木目黒区長・大塩教育長が挨拶。
13名の方々を代表しての当事者の方話しは、素朴で働く喜びがあふれていて心をうたれた。
乾杯のあいさつをさせていただく。
また御門屋 針谷社長など多くの支援されている地元の皆様、また障がい者支援の関係者など大勢の方々との交流を深める会となった。
2010年10月22日
愛媛県・南予地域の道路等のインフラ整備を!
道路インフラ整備の要望=22日 東京都
朝、8時30分から厚生労働部会が行われ、国会提出法案の説明をヒアリング。
国対役員会の後、議員総会。山口代表から国会論戦に先頭に立ち取り組もうと!の力強い挨拶。
その後本会議。
午後から国会事務所に石橋宇和島市長・福本市議会議長、清水愛南町長・吉村町議会議長などが来訪され、下記の要望をいただく。
平成20年の予算委員会で質問した事も含め、しっかり対応を進める事をお話しする。
1.「命の道」である国道56号一本松・宇和島間の整備促進
2.高規格幹線道路等のネットワークの整備促進など
・四国8の字ネットワーク等の整備促進
・地域高規格道路の整備促進
3.四国縦断・横断自動車道の整備促進について など等。
2010年10月21日
「新卒者就職支援・独居高齢者支援策」など細川大臣に質問
政府の課題を指摘=21日 東京都
終日、厚生労働委員会が行われた。細川大臣の所信について質問。
下記の内容で50分間、政府の取組みについて、課題を指摘し、政策・提言を訴える。
Ⅰ.ハンセン病問題に関する件について
1.多摩全生園などの地域開放の進捗状況はどのようになっているのか。
2.大島青松園の官用船の対応状況はどのようになっているのか。
Ⅱ.新卒者の就職支援について
1.青少年雇用機会確保指針の改正にどのように取り組むつもりか。
2.中小企業とのマッチングをどのように行うつもりか。
3.地方の就職機会の拡大にどのように取り組むつもりか。
4.経済団体や業界団体への働きかけをどのように行うつもりか。
5.ハローワークの活用をどのように周知するつもりか。
6.社会保障の分野でどのように雇用を創出するつもりか。
7.訓練・生活支援給付金制度の恒久化に向けてどのように取り組むつもりか。
Ⅲ.独居高齢者への支援策について
1.高齢者の単身世帯の状況について伺いたい。
2.地域福祉計画の策定状況はどのようになっているのか。
3.地域包括支援センターの見守り活動の充実強化にどのように取り組むつもりか。
4.安心生活創造事業の取り組み状況について報告いただきたい。
5.地域活力の活用について見解を伺いたい。
Ⅳ.うつ病対策について
1.職場におけるメンタルヘルス対策検討会の報告書の概要を伺いたい。
2.労働安全衛生法の改正について見解を伺いたい。
3.リワーク支援事業のカウンセラーを拡充すべきではないか。
2010年10月20日
「社会保障トータルビジョン検討会」で中間報告
社会保障トータルビジョン検討会=20日 東京都
香川県都築県議・広瀬県議が来訪。障がい者年金などの市民相談について、厚労省からヒアリング。
また故郷、愛媛県八幡浜市の大城市長も来訪。八幡浜港バリアフリー対応旅客施設の拡充など伺う。
四国の西の玄関口である八幡浜港は、臼杵・別府航路が就航し、年間40万人の乗降客が利用。昭和48年建設の建物は老朽化して、高齢者・身体障がい者などの利用に配慮した構造でない。
安全で機能的なフェリーターミナル整備へ、取り組む状況を聞き、課題など伺う。対応を進めてまいりたい。
公明党肝炎対策PTが開かれ、全国B型肝炎訴訟原告団(谷口三枝子代表)の皆様からの要望など伺い、意見交換を進めた。
「財源論でない。キャリアにもきちんとした賠償を」など国の「命の線引き」「患者切り捨て」に批判が。B型肝炎訴訟 国は被害救済に一層の努力が求められる。
夕方「社会保障トータルビジョン検討会」が開かれ、5つの分野の中間報告を実施。担当分野の「障がい者」「貧困と格差」について説明・意見交換を進める。
明日、厚生労働委員会での50分の質問。事前レクも含め、遅くまで準備を進める。
2010年10月19日
「お泊りディ」の制度化についての要望を伺う
要望書をいただく=19日 東京都
「お泊りディ」の制度化を心配する介護現場の会の方々が事務所に来訪。
「宿泊付きデイサービス」制度化についての要望書をいただき、概要をうかがう。公明党山口県宇部市長谷川耕二市会議員が同席。
岩手県・宮城県・東京都・名古屋市・大阪市・山口県など全国で、地域密着型の小規模ディサービスを運営している事業者の皆様。
約20年前から制度のない中、地域住民とともに手づくりで宅老所や民間ディサービスとして立上げ、運営。介護保険施行後は、認知症専用の通所事業所や小規模通所事業として継続運営してきた。
認知症のお年寄りは、夜間に不安や混乱が激しくなるため、介護保険外で自主事業の「泊り」を実施し、お年寄りの在宅を支えてきた。
今回浮上した「宿泊付きデイサービス」の制度化について慎重な議論と制度施行を望む下記の要望・提案である。
【「宿泊付きデイサービス」制度化について】
厚労省は8月23日介護保険部会で「お泊りディサービス」を提案し、20011年度概算要求で「家族介護者支援(レスパイトケア)の推進」として施設整備費にあたる内容として100億円が盛り込まれた。
【宿泊付きデイサービスの評価・見解】
社会サービスとして必要であり、当事者の生活支援として重要な実践であると評価されたものと理解し、「制度化」そのものには賛成。
しかし制度化されるのは余りに性急すぎる。全国で取り組まれた経過、現状の成果と問題点、課題など実態を調査し、時間をかけた慎重な議論とモデル事業実施などの準備期間を充分に必要。
また現在検討されている制度化のあり方について反対。家で暮らせなくなる高齢者を増やすことになるのではないかと危惧する。
【危惧する点】
1.運営費の問題
2.マネージメントの問題
3.給付上限の問題
(利用者は限度額を超え、宿泊どころか、通所も制限されない)
4.制度化によって自主事業が制限されないか?
【提案】
1.これを機会に、ショートスティのあり方を抜本的に検討を。
2.まず国のモデル事業を認知症通所介護事業所において実施。財源は東京都と同様一般福祉財源で対応を。
3.もし「宿泊付きデイサービス」が制度化されても、これまでの「泊り」の自主事業を制限しないで。
切実な声を真剣に受けとめ、様々な観点から研究してまいりたい。
2010年10月19日
桜島火山活動対策の積極的な推進を!
桜島火山活動対策協議会からの要望=19日 東京都
厚生労働委員会で開催され、細川大臣の所信を聞く。次回21日(木)の厚労委員会で一般質問の予定(質問時間50分)
その後、「桜島火山活動対策議会協議会」の方々からの要望を伺う。
鹿児島市議会上門議長や垂水市・霧島市さらに鹿児島県議会の柴立副議長・成尾県議(公明党)など九州から来られる。
要望の背景は、
桜島の火山活動は、平成21年観測史上最多となる548回の爆発が発生したが、本年は9月末時点で781回と既に大幅に上回っており、今後さらに噴火活動が活発化し、溶岩の流出の可能性も考えられる。
桜島周辺に暮らす住民は生活に大きな不安は抱えていることから、降灰や火山ガス等による被害を最小限に食い止め、地域住民の日常生活の安全、経済活動の安定を図るために、下記10項目について要望をうかがう。
1.桜島火山観測・研究の推進
2.桜島周辺の道路整備の促進
3.砂防事業
4.治山事業
5.健康対策
6.桜島火山対策に対する経費の財源措置
7.降灰除去事業
8.降灰防除施設の整備
9.火山活動周辺地域防災営農対策事業
10.海面環境保全事業(桜島軽石等除去事業)
東副代表以下国会議員より公明党としてしっかり対応していく事をお話しする。