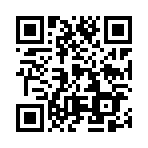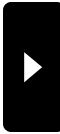2010年04月30日
上海万博開会式・国営放送で生中継
中国初の本格的な国際博覧会となる上海万博が5月1日に開幕する。史上最多となる189カ国と57の国際機関が参加し、「より良い都市、より良い生活」をテーマに持続可能な発展の必要性を訴える展示やイベントが予定されている。
本日(30日)には会場内で、胡錦濤国家主席やフランスのサルコジ大統領夫妻や韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領ら約20カ国の首脳級が参加する開会式が行われた。ちょうど済南市のホテルで生中継の国営放送CCTV)で開幕式を鑑賞する。
オープニングはジャッキーチェンの歌から。
イタリアの国際的なテノール歌手、アンドレア・ボチェッリさんら五大陸を代表する歌手が歌声を披露。
アジア代表は谷村新司さんが務め、中国でも広く知られるヒット曲「昴」を熱唱。大型スクリーンで幻想的な映像と踊りがさらにムードを盛り上げる。
屋内から屋外荷移動。そのスケールがすごい。会場内を流れる黄浦江で10万発以上の花火が打ち上げられた。大型スクリーンやレーザー光線・放水など駆使して大変華やかな祭典。映像からでもその規模に驚く。
上海万博は、10月末までの184日間。来場者は、史上最多の約6400万人だった1970年の大阪万博を上回る7000万人と予測する。
本日(30日)には会場内で、胡錦濤国家主席やフランスのサルコジ大統領夫妻や韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領ら約20カ国の首脳級が参加する開会式が行われた。ちょうど済南市のホテルで生中継の国営放送CCTV)で開幕式を鑑賞する。
オープニングはジャッキーチェンの歌から。
イタリアの国際的なテノール歌手、アンドレア・ボチェッリさんら五大陸を代表する歌手が歌声を披露。
アジア代表は谷村新司さんが務め、中国でも広く知られるヒット曲「昴」を熱唱。大型スクリーンで幻想的な映像と踊りがさらにムードを盛り上げる。
屋内から屋外荷移動。そのスケールがすごい。会場内を流れる黄浦江で10万発以上の花火が打ち上げられた。大型スクリーンやレーザー光線・放水など駆使して大変華やかな祭典。映像からでもその規模に驚く。
上海万博は、10月末までの184日間。来場者は、史上最多の約6400万人だった1970年の大阪万博を上回る7000万人と予測する。
2010年04月30日
山東省・済南市の地方視察
済南空港=30日 済南市
午後北京空港からの飛行機便で山東省の省都済南市へ。約50分の飛行時間。小さな飛行機で少々不安であったが、安全に到着。タラップから降りると、緑の木々。飛行場を自転車で走る光景に北京空港との違いを感ずる。
山東省(さんとうしょう)は、中国の省の一つ。略称は周代の国名より魯。山東とは太行山脈の東方の意。北には渤海、東には黄海があり、黄河の下流に位置する。人口9041万人、面積156,700平方キロメートル。省都は、済南。他に青島、泰安などの主要都市がある。
済南市(さいなんし)は中国の山東省に位置する副省級市。山東省の西部に位置し、省都として省内の通商、政治、文化の中心としての地位を占める。市中を黄河が流れ、南には泰山が控えている。人口のほとんどは漢族であるが、満族や回族なども居住している。
済南市の印象は超高層ビルやマンションの建設工事が見られ、経済の発展が感じられる。一方、緑の山々、数多い自転車など北京と比べ、庶民的。
北京だけでなく、地方にも出向き交流を深める事の大切さを少し、垣間見た。
山東省生まれの徐顕明(じょ・けんめい)全人代常務委員会委員が出迎えに来られた。徐さんは中国政法大学学長や山東大学学長も歴任され、全人代の法律委員会委員でもある。
明日は、山東省の曲阜・泰山を視察さらには山東省要人と会見等、地方の中国理解につなげてまいりたい。
2010年04月30日
北京オリンピック・メインスタジアム「鳥の巣」見学
北京国家体育場=30日 北京
午前中北京市内の北京オリンピックのメインスタジアム「北京国家体育場」愛称「鳥の巣」を視察。
2008年12月訪中の時も見学して2回目。しかし前回は氷点下の寒さ。
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/cat72/cat118/2008/12/21_1062.html
本日は大変温かく議員団の方々と視察。
最大収容予定人数は91,000人で、オリンピック終了後は施設の改修が行われ、座席数は8万人規模だがスケールに驚く。概観も大変美しい建築物。
オリンピック球場を直接見学すると感動のオリンピックの場面が改めてよみがえる。
北京市内の超高層ビル・海外企業の進出。マグドナルドが2店も見えるなど海外企業の進出。車社会で渋滞の市内。一方格差も激しい。明日から開幕の上海万博。中国から目が離せない。
2010年04月29日
日中議員会議で人文交流発言・桁違いのスケール人民大会堂を見学
人民大会堂の外観=29日 北京
全国人民代表大会(全人代)は諸外国の国会に相当する。全人代の人数は2987名で任期5年。委員長は呉邦国(ご・ほうこく)。副委員長は13名。李建国(り・けんこく)も副委員長で秘書長を兼務されている。曹衛洲(そ・えいしゅう)は副秘書長。
午後は第2セッションが行なわれ、下記テーマで意見交換を進めた。
・日中経済貿易関係
・人文交流
・気候変動
・省エネルギー・環境保護
午後は、人文交流のテーマで発言する。
テーマは、「文化・青年の各分野で友好交流促進について」
2008年日中青少年交流年で日本から高校生・大学生など1000名が訪中し、温家宝総理出席の閉会式に参加した。高校生が地方視察・ホームスティなど中国を身近に感じ、親近感をもった感想を通し、青少年交流の大切さを話す。
さらに文化交流では、身近な体験として民音の招聘で「中国雑技団」の素晴らしい公演を四国の高松で鑑賞した事を通じ、全国の都市で大反響。中国文化を紹介する民音公演はこれまで250万人以上が鑑賞。明年は今回参加されている江亦曼(こう・えきまん)氏の出身地の「陝西省歌舞劇院」賀公演の予定である事。東京富士美術館の三国志展・故宮展など文化・芸術の交流が日中交流の大きな推進役となっている事を紹介。様々な分野での民間交流の裾野を広げる事の大切さを訴えた。
休憩の時間も多くの議員と交流。
中国人民解放軍政治委員・全人代農業・農村委員でもある山東省の李殿仁(り・でんじん)。全人代教育文化衛生委員会委員の馬力(ば・りき)女史などとも懇談。さらに午後の中国側中心者・曹衛洲(そう・えいしゅう)副秘書長とも親しく懇談を重ねる。
9時から17時30分まで、中日の議員団が様々な分野で意見交換。大変貴重な経験を積ませていただく。
その後、人民大会堂の中を見学。
毛沢東の生まれた湖南省の部屋や鄧小平の出身地の四川省の部屋を見学。こうした部屋が省の数34の部屋があるとの事。全国から集まる全人代の委員が使用するという。
また全人代のメンバーが集まる大会議場では約1万人収容でき、そのスケールにびっくりする。
夜は在中国大使館からのブリーフを兼ねた夕食会に参加。中国の現状を大使館の梅田公使から伺う。
2010年04月29日
第4回日中議員会議で発言(日中交流・北朝鮮問題・国際貢献)
国際及び地域の主な主題について発言=29日 北京
訪中2日目。
第4回日中議員会議が人民大会堂・安徽庁(あんきちょう)で行なわれた。
最初に、李建国団長・大石団長からの基調提言の後、下記内容で議事が進む。午前中は、第1セッション。
・日中交流・議会交流
・国際及び地域の主な問題
・食品問題がテーマ。 会議は、同時通訳で状況は逐次把握できる。
午前中では2回発言する。
・日中関係・議会交流では日中交流の歴史(中国側は曹衛洲氏)が披露され、私も日中交流の公明党との歴史と青年交流の大切さを訴える。
特に公明党の創立者の1968年9月の『日中国交正常化提言』の時代状況(国交もなく、冷戦が東西に分断。中国も文化大革命の混乱の時代)の中、①日中国交化の正常化②広く対中経済・文化交流促進の提言を表した事。
中でも、日本の1万数千人の青年に向けて
『やがて諸君達が社会の中核となったときには、日本の青年も中国の青年とともに手を取り合い明るい世界の建設に笑みを交わしながら働いていけるようでなくてはならない。この日本、中国を軸として、アジアのあらゆる民衆が互いに助け合い守りあっていくようになったときこそ、今日アジアをおおう戦争の残虐と貧困の暗雲が吹き払われ、希望と幸せの陽光がさんさんと降り注ぐ時代である。』との創立者の言葉を紹介。
その後の1974年12月の周総理との初会見。創価大との留学そして周桜の経緯。1985年3月、共青団の第一書記であった胡錦濤国家主席と共に創価学会青年部との交流協定に正式調印された歴史を通じ青年と交流の大切さを話す。
最後に周恩来総理の言葉
『両国の伝統的な友情が流れ続ける長江のようにとうとうと絶えることなく、高くそびえる富士山のように永遠に存在し続けることを心から願っております。』を通じ、総理の心を心として万代の日中友好に邁進する訴えさせていただく。
また国際及び地域の主な主題は日本側を代表して下記提言について話す。
発言内容(議題:国際及び地域の主な問題) 山本博司
公明党の山本博司でございます。今回、日中議員会議の場に初めて参加させていただき、また発言の機会をいただき、心から感謝申し上げます。中国訪問は2回目となります。初めての訪中は、2008年12月に北京で行われました日中青少年友好交流年の中国側閉幕式に当時の福田康夫首相と共に参加させていただいたときです。その際、真心から大変親切に対応いただいた関係の皆様に心より御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
私は日本との縁深い隣国中国に大変親しみを持っており、大学時代、中国の政治を専攻しておりました。私の尊敬する人物は貴国の周恩来総理であります。公明党と貴国との交流は、公明党の創立者、池田大作名誉会長が1968年に発表した「日中国交正常化提言」から始まり、様々な交流を通じ、本日を迎えられたことは私にとっても感激であります。ありがとうございます。
私からは、国際及び地域の主な問題に関して、北朝鮮問題と途上国支援を含めた国際貢献について発言いたします。
北朝鮮は国際社会の強い反対にもかかわらず、2回の核実験を強行しました。核をもてあそぶような北朝鮮の行動は断じて認めることはできません。我々は国際社会と連携して北朝鮮に対して六者会合に一刻も早く復帰することを強く求めたいと思います。
貴国は北朝鮮の六者会合への復帰を促すため、2009年10月には温家宝総理が、本年2月には王家瑞(おうかずい)中連部長がそれぞれ訪朝して北朝鮮の関係者と協議するなど地道な努力を重ねておられます。六者会合の議長国としての再開に向けた様々な努力に心より敬意と感謝を申し上げます。我が国も関係国と緊密な連携を図りながら、六者会合再開を北朝鮮に働きかけてまいります。貴国におかれましても引き続き今一歩の働きかけを是非お願いするものでございます。
北朝鮮による日本人拉致事件は、我が国の主権及び国民の生命に関わる重大な問題であります。私は、参議院の拉致問題特別委員会委員として拉致被害者の家族の皆様とお会いし、悲痛な声をお聞きいたしました。我が国は、六者会合のプロセスを通じて、核、ミサイル、拉致の問題を包括的に解決することを望んでおります。この問題につきましても、貴国の支援を是非お願い申し上げます。
次に途上国支援を含めた国際貢献について触れたいと思います。
まずはメコン地域への支援です。
以下発言ではメコン地域支援とアフリカ支援にふれる。(内容省略)
午前中のセッションの後、全員での記念撮影。
2010年04月28日
日中友好の金の橋を!李建国全人代副委員長主催の歓迎宴
李建国副委員長=28日 中国北京
李建国全人代常務委員会副委員長(秘書長)主催の歓迎宴が人民大会堂・香港庁で開催された。
ホテルから有名な天安門広場を通り、人民大会堂へ。
日本からの交流議員団と中国側の議員団の紹介の後、李建国副委員長の歓迎の挨拶。そして乾杯の後、中国の議員の方々と交流を深める機会となった。
李建国(り・けんこく)副委員長は山東省出身。今回地方の視察で山東省を訪問の予定。公明党の若い国会議員の方々との交流が中日の万代の友好の絆が深まるなど公明党に期待をいただく。
隣の席は広東省出身の何少苓(か・しょうれい)全人代代表環境・資源保護委員会委員。
1962年生まれで最年少の山東省出身の謝経栄(しゃ・けいえい)全人代財政経済委員会委員。
黄鎮東(こう・ちんとう)全人代内務司法委員会主任委員。江亦曼(こう・えきまん)全人代外事委員会委員(中国赤十字常務副会長)等など。全人代の要職を歴任されている方々と友好を深めた。
お会いする方々が、公明党と創立者の話題に。日中友好の礎『井戸を掘った人』を築かれた創立者への尊敬と共に後に続く青年に期待を託されていた。
1968年9月8日の創立者の日中国交正常化提言は特に国交もなく、冷戦が世界を東西に分断・中国も文化大革命の混乱の時代に『日中国交正常化・広く対中経済・文化交流促進』との先見的な提言であった。そして1974年周恩来総理との会見で、留学生の受け入れを創価大学が担う事になった。その1期生が程永華(てい・えいか)駐日大使。
曹衛洲(そう・えいしゅう)副秘書長は共産主義青年団中央(共青団)国際連絡部部長を歴任し、1985年 共青団の第一書記であった胡錦濤国家主席と共に創価学会青年部との交流協定に正式調印された。創立者や胡主席の見守る中で交流協定に調印された様子を語ってくれた。
今回の通訳の方々も孟さんのように創価大留学生が多く担当されており、改めて、『日中友好は百年の計です。若い人達が交流し、理解しなければ本当の友好は築けません』との創立者の言葉にその姿を実感した。
訪中1日目であったが、多くの金の思い出と感銘を受ける機会となった。
2010年04月28日
日中議員会議団として中国へ交流(訪中1日目)
北京空港=28日 中国北京
早朝羽田空港へ。
第4回日中議員会議 日中交流議員団として4月28日から5月2日まで中国北京・山東省(済南)の予定。
日本の参議院と中国の全国人民代表大会との定期交流の一環で今回4回目。メンバーは、民主党5人・自民党3人・公明党1名の9名(団長は民主党大石議員・副団長は自民党浅野議員)。
12時30分に北京空港着。(北京の時間。時差は1時間)
曹衛洲全国人民代表大会常務委員会副秘書長が空港まで出迎えに来られる。通訳は2年前の訪中のさいの孟さん。大変懐かしく2年前真冬に万里の長城を登った思い出がよみがえった。
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/cat72/cat118/
その後ホテルに移動。午後、短時間市内見学。高層ビルと車社会の中国。急速な発展で活気が感じられる。
夕方から人民大会堂・香港庁で李建国副委員長主催の歓迎宴が開催された。
2010年04月27日
障がい者福祉充実へ!障害者自立支援法改正案を衆議院に提出
障害者自立支援法改正案提出=27日 東京都
本日、障害者自立支援法改正案を衆議院事務総長に自民・公明両党で提出をした。
民主党は、障害者自立支援法を廃止して総合福祉法の制定を検討しているが、総合福祉法の実施は平成25年年8月とかなり先となる。
障害者団体からは、総合福祉法成立まで待てない。課題点の改善が必要との意見が多い。具体的に昨年の改正案の内容の早期実施を求めており、今回改正案をベースに2項目(目的規定の改正と成年後見制度利用支援事業)を追加し、本日衆議院に提出した。
昨年の通常国会に提出され廃案となっていた障害者自立支援法の改正案の内容は、相談支援の充実や障害者自立支援協議会の法定化、グループホーム・ケアホーム利用の助成、重度視覚障害者の移動支援サービス、障害児支援の強化などについて改善策が数多く示されていた。
民主党や与党・野党を含めて超党派で成立をめざし、障がい者支援の充実に向けて進めてまいりたい。
2010年04月27日
脳卒中対策強化へ!国民健康保険法案で大臣に質問
質問=27日 東京都
厚生労働委員会が終日行なわれた。「国民健康保険法案」について40分間質問をする。
1つは脳卒中対策強化について「血栓溶解療法(t-PA療法)」の普及・「脳卒中における救急搬送と医療の連携」「リハビリテーションの充実」について政府の見解を伺う。
後半は今回の法案について総報酬制の問題点について指摘する。
(下記質問内容)
Ⅰ.脳卒中対策について
1.「t-PA療法」の普及に努めるべきではないか。
初めに法案に入る前に医療の問題に関連して、脳卒中対策についてお聞きしたいと思います。がん、心臓病に次いで日本人の死亡原因として3番目に多いのが脳卒中であります。先日もプロ野球のコーチが突然にくも膜下出血で倒れ亡くなられるという悲しいニュースがありました。
最近では、医療技術の進歩に伴い、脳卒中の患者の方は、発症から急性期、回復期を経て維持期に至るまでに、適切なリハビリを行うことによって回復し、社会復帰が可能となるケースも多くなっております。発症の予防とともに、患者の様態に応じて切れ目のない医療体制のネットワークが構築できるよう、地域での対策が求められていると思います。
先日、最先端の取り組みを行っている横浜市脳血管医療センターを訪問し、視察をするとともに、患者や家族の皆さま方から貴重なご意見、ご要望をお聞きする機会がありました。
この横浜市脳血管医療センターは脳卒中専門病院として急性期医療から回復期のリハビリテーションまで一貫した治療を提供しております。回復期のリハビリ病棟の在宅復帰率は83%と全国平均の66.1%と比較しても充実しております。また、24時間365日体制で、専門医がCT、MRI等の機器を活用し、診断、治療を行っておりました。
そこで、この視察の中でお聞きした中から、いくつかお聞きしたいと思います。まず、新しい治療法の普及促進について伺います。
脳卒中の死者のうち約6割を占める脳梗塞は、発症から3時間以内ならば「血栓溶解療法(t-PA療法)」で後遺症が残らず劇的に改善する可能性があり、この療法は平成17年に保険適用されております。しかし、副作用の危険が高く、条件を満たした医療機関だけが実施可能といわれており、治療を受けているのは、年間約21万人と推計される患者全体のうちのわずか2%に限られております。普及が進まない大きな要因は一般市民への周知が不足していることと、救急搬送体制が脳梗塞治療に適した体制になっていないことによるといわれております。
そこで、この「血栓溶解療法(t-PA療法)」について、普及促進に努めるべきではないかと考えますが、現状の対応状況についてご報告を頂きたいと思います。
2.脳卒中における救急搬送と医療の連携体制はどのようになっているのか。
さらに、脳卒中患者の命が発症急性期の対応によって左右されており、救急搬送と医療の連携が重要です。横浜市では、平成20年度からの試行実施を経て、21年度から脳血管疾患に対応した救急医療体制を正式運用し、30ヶ所の医療機関における受入れ体制やt-PA療法に対応可能な救急搬送体制を整備しております。
こうした先進的な体制を全国的に普及させることが大事であり、救急搬送を管轄する総務省と医療を整備する厚生労働省との連携の仕組みを作ることが求められております。
わが党は、平成19年に「救急医療対策推進本部」を立ち上げ、救急医療の現場視察や実態調査を行い、脳卒中などの救急医療体制の整備を総務、厚労の両省に要請し、 積極的に働きかけた結果、昨年5月、消防機関と医療機関の連携で患者を適切な医療機関に迅速に搬送するための消防法改正も実現いたしました。こうした連携体制の充実が重要ですが、現状はどのようになっているのか、ご説明いただきたいと思います。
3.リハビリテーション支援の拡充に取り組むべきではないか。
また、病院での治療を経て、回復期から維持期のリハビリテーションの充実が、地域生活を行う上で、患者のみならず家族の生活にも大きく影響を与えます。
墨田区では、平成20年度より、医師会と行政及び地域リハビリテーション支援センターである東京都リハビリテーション病院との連携により「在宅リハサポート医制度」が区の負担により利用者は無料で実施されております。リハビリの必要な区民の方が、住み慣れた地域で、安心してリハビリができるよう、医療と介護の両面から支援策がとられております。
全国的に、回復期における医療でのリハビリと維持期における介護でのリハビリのいずれもいまだ絶対的に不足しているとも指摘されており、平成24年の医療と介護の報酬改定の際にはこうした点にも配慮が必要であると思います。
今回の医療の報酬改定でも対応がなされていると思いますが、さらなる報酬改定を求めます。また医療でのリハビリが180日の日数制限が設けられ、患者の皆様から機能を維持・改善していくために大変不便との声もいただいております。
こうした様々な課題解決へ、さらにリハビリテーション支援の拡充に取り組むべきと考えますが、認識を伺いたいと思います。
4.総合的な脳卒中対策が必要ではないか。
これまで見てきたように、救急搬送体制の充実、専門的な医療機関の質・量両面での確保、リハビリ施設の整備、国民への意識啓発など、さらには財源の確保といった脳卒中対策には省庁を超え、地方自治体や医療保険者、医療従事者など多くの国民各位の協力を得なければ解決できない課題が数多くあります。
患者会の皆さまからは、「がん対策基本法」の経験に学び、「脳卒中対策基本法の制定」を強く要望され署名活動も展開されております。
こうした声を受け、国を挙げて力を注ぐためにも、総合的な脳卒中対策が必要ではないかと考えますが、大臣の認識を伺いたいと思います。
Ⅱ.医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法の一部を改正する法律案について
1.医療保険部会での議論をもっと丁寧に行うべきではなかったのか。
2.高齢者医療制度の見直しの前に提案した理由はなにか。
3.健保組合等の合意を得る努力をもっとすべきではなかったのか。
4.総報酬制の導入をやめるべきではないか。(大臣)
5.財政力の弱い健康保険組合の負担軽減をどのように考えるのか。
6.市町村国保の抜本的な問題解決に向けてどのように考えているのか。(大臣)
7.市町村国保の広域化、都道府県単位化をどのように進めるつもりか。(大臣)
8.国民皆保険制度の堅持に向けた大臣の見解を伺いたい。(大臣)
2010年04月26日
明日の厚生労働委員会での質問準備
質問レク=26日 東京都
明日の厚生労働委員会で国民健康保険法案について質問の予定。時間は15時40分から16時20分まで、40分間。
質問レクを実施し、準備を進める。
日本の医療保険制度は国民皆保険制度がとられており、安心して適切な医療が受けられ、国民生活の安定に大きな役割を果たしている。
しかし今回の改正法案は、財政力の弱い健康保険組合にとって、健康保険組合や共済組合の加入者に負担を肩代わりするような制度改正になっており、大変危惧されている内容である。そのため、政府への具体的な質問を通じて、論点を明確にし、対応改善へ進めてまいりたい。
また脳卒中対策として、脳卒中患者・家族会の方々の要望についても改善を求めて、質問をしたい。
夕方、障がい者福祉委員会が開催された。「障がい者グループホーム(GH)の火災事故について」日本グループホーム学会から説明を受け、問題点に対し厚労省、消防庁、国土交通省から見解を求めた。
第1回目で、現状の問題点の整理を中心に現場の皆様の声を伺う。地域生活中心へ、グループホームの拡充を進めている中、消防法、建築基準法など法律の壁により、基準があいまいな為、自治体の格差がありGHの建設中止などの課題が出ている。
神戸大学大学院大西准教授からは、グループホーム防火の制度的課題について①火災安全性評価法②求められる防火基本性能③GHの防災安全システム不在のため研修の実施・イメージトレーニング(FIG)など、わかりやすい事例から、課題への解決策を提言された。貴重な提言である。
2010年04月25日
引きこもり支援拡充へ!地域の皆様との国政懇談会
国政懇談会=25日 香川県
午後より、高松市に移動し、あなぶきホールで上映している映画「アンダンテ稲の旋律」の上映会へ。引きこもりから抜け出し自立する若い女性が主人公。「食と農と大地。人間再生のドラマ」である。
主催の中心として活動するKHJ香川県オリーブの会(引きこもり家族会)川井理事長とお会いし懇談する。山田高松市議も同席。引きこもり支援の活動の課題と対策について伺う。
さらに高松市内の今里町東福寿会 廣瀬会長など地域の町会の方々に国政報告。また質問など自由に伺う。
「四国の高速道路、フェリー会社支援、民主党のマニフェスト違反、医療、介護、地域活性化など」活発な意見要望が出る。地方の声・特に四国固有の課題など積極的に発信して欲しい等、地元国会議員また公明党への期待が大きい事を痛感。
2010年04月25日
陸上自衛隊第14旅団総隊4周年・善通寺駐屯地開設60周年行事
観閲式でのあいさつ=25日 香川県
午前中、雲1つない青空の下、第14旅団総隊4周年・善通寺駐屯地開設60周年記念行事が開催され、自衛隊員・家族、市民の皆様、過去最高の約1万8千人が参加された。
陸上自衛隊第14旅団は、国民の生命・財産を守るため、日頃から各地で様々な活動を行っている。四国4県の防衛警備、災害情報、民生協力等の任務を有し、昭和56年3月から約25年間にわたって築いてきた「第2混成団の伝統」を受け継ぎ平成18年3月に編成された。
善通寺(香川県善通寺市)、松山(愛媛県松山市)、高知(高知県香南市)、日本原(岡山県奈義町)の4つの駐屯地および北徳島分屯地(徳島県松茂町)に駐屯している。
来賓代表として、日頃の防衛・災害活動など懸命に取り組む自衛官に敬意と感謝の挨拶をさせていただく。
その後隊員約1300名、戦車・装甲車等車両約110両による観閲後進。さらに訓練展示として第14偵察隊の見事なオートバイドリルや空挺団の空挺降下そして音楽隊の素晴らしい演奏が繰り広げられた。
市民にとって身近に自衛隊が感じられる機会となったのではと実感。
正午からは香川県防協会及び善通寺市自衛隊協力会主催の祝賀会が行なわれ、鏡割りに参加。地元善通寺の方々、愛媛・高知・徳島から来られた方々などと交流を深める一時となった。
2010年04月24日
原爆被爆者・パーキンソン病・介護・障がい者など現場の声を伺う
広島市内の風景=24日 広島市
午前中、原広島市議と市内を訪問。原爆症被爆者の方からは、原爆症認定申請について昨年3月に申請してまだ結論が出ておらず、早急な対応を求められる。被団協の方らも大量の申請却下の課題も伺っており、今後政府にしっかり対応を求めていきたい。
東区では全国パーキンソン病友の会 広島支部副支部長の水野宅を訪問。後藤支部長・木村副支部長・田中幹事など友の会の方々と懇談。パーキンソン病の治療や就労の課題など貴重なお話しを伺う。
いつも国会の請願申請で事務所での懇談であったが、ご自宅を訪問でき、直接皆様と現場の声が聞け、大変嬉しく、感謝です。
西区では、介護講座など各種講座を展開する(株)福祉情報センターを田川県議・原市議と訪問。小林社長・松嶋執行役員等から介護研修などの課題・要望を伺う。
「緊急人材育成・就職支援事業」で山陰初のエステ講座を開設。主婦など雇用増が見込まれ、大変喜ばれている。また介護分野での研修定着への取組みについて独自の研修を取り入れる内容など大変感銘を受ける。
佐伯区では米津市議・原市議と介護現場・特別養護老人ホーム「やすらぎの里」を見学。槙野施設長や介護従事者また利用者の皆さんの声を伺う。小中学生への福祉教育の大切さ・地域との連携など貴重なご指摘をいただく。介護従事者の待遇改善の取り組みについてさらに推進の要望も伺う。
廿日市市細田市議とは、障がい者の作業所を訪問。施設長に障がい者施策について、課題・要望を伺う。
本日は、原爆症・難病・障がい者・介護などの現場の方々の声を伺い、大変有意義な1日となった。
広島駅から新幹線・マリンライナー号で高松へ。久しぶりの高松泊。
2010年04月23日
「谷あい正明を励ます会(大阪大会)」が盛大に開催
谷あい正明を励ます会=23日 大阪府
東京駅から新幹線で大阪に移動。
夜、「谷あい正明を励ます会」が開催。大勢の皆様が参加され、「谷あい頑張れ!」とのエールをおくっていただく。
発起人・中国・四国公明会全員登壇し、代表して斉藤政調会長が挨拶。
公明党山口代表からは鳩山政権のうそと朝令暮改の末期政権を糾弾。
谷あい正明参議院議員が若者らしい凛々しくあいさつ。
倉敷市伊東香織市長の乾杯に続き、懇談の場に。
途中、私から挨拶と大阪選挙区石川ひろたか候補を紹介。同じく大阪選挙区に挑戦する若武者石川ひろたかが、皆様に必死の訴え。
来賓からは黒田玉野市長など激励の挨拶が続く。
石川候補や谷合議員を紹介する中で、青年の党公明党への期待が強い。第3極の公明党の役割は大きい。
終了後、広島へ向かい新大阪を出る。
2010年04月23日
「鳩山首相の政治資金資料の提出拒否発言」に国民の不信倍増
浜田参議院議員=23日 東京都
雨の東京。午前中参議院本会議で、鳩山総理訪米報告の質疑が行なわれた。公明党から浜田参議院議員が登壇。最初に総理に「元秘書の裁判が終わったら資料を取り戻して説明すると言ったのを翻したあなたはウソつきだ」と厳しく糾弾。議場が騒然となる。
鳩山首相は、3月3日の参院予算委員会では『資料を皆さまに見ていただきたい』と答弁。これが、3月31日の公明党の山口那津男代表との党首討論で「国民の皆さまにどこまでしっかりお示しできるか検証していきたい」と一歩後退。
4月21日の党首討論に至っては「資料の提出は必要ないもの」と従来の発言を一転させ、まったく180度違う発言に。これでは、何が真実なのかわからず、この首相には何を聞いてムダ。国会審議を冒涜し、国民を愚弄している。
こうした鳩山首相の無責任な対応に、マスコミ各社も厳しく批判している。23日付の読売社説で、「前言はすべて嘘だったのか。首相はただちに調査を開始して、巨額資金の使途を可能な限り国民の前で明らかにすべきだ」。
産経新聞は「首相が不誠実な対応を示したのは21日の党首討論だ。公判終了後に関係資料を提出するとしてきたこれまでの国会答弁を翻し『基本的には必要ない』と述べた。勝場被告に、証人喚問に応じるよう促すことも拒否した」と厳しく断じている。徹底追求してまいりたい。
2010年04月22日
地域主権法案の連合審査会で保育について質問
連合審査会=22日 東京都
今日は昨日よりも大きく気温が下がり冬に逆戻り。
午前中は地域主権法案の総務・厚労委員会の連合審査会が開催され、30分間質問に立つ。
保育制度に関し、国と地方の関係、また保育サービス充実策、認定子ども園地方裁量型の支援など四国・中国の保育現場をまわった生の声を総務大臣・厚生労働大臣に訴えた。
午後からは厚生労働委員会・政調全体会議と1日中国会での審議・会議となった。
(質問項目・内容)
1.子ども手当について
1.今年度の子ども手当には、児童手当の仕組みを残し、地方負担があることをどのように考えるのか。(総務大臣)
公明党の山本博司でございます。本日は、地域主権法案に関連して保育制度についてお聞きしたいと思います。この保育制度の改革は就学前の子どもたちや子育てをする親たちの社会進出にとっても重要な課題でありますので、総務、厚労の両大臣のご認識をお伺いしたいと思います。 まず、子ども手当に関連して伺います。
今年度の子ども手当は、児童手当の仕組みを残すこととなり、地方負担分約5700億円が財源の一つとなっています。マニフェストでは、全額国費負担としていた中、いわゆる昨年12月23日の4大臣合意で決まったものであります。この合意になるまでは、総務大臣は、「保育所運営を地方でやり、浮いた国費で子ども手当てを」との趣旨の発言をされていました。
この今年度の財源について、地方負担分を残したことは間違っていなかったとお考えなのか、総務大臣の現時点でのご感想をお聞きしたいと思います。
2.来年度以降の子ども手当の財源をどのようにするつもりか。(厚労大臣・総務大臣)
3.現金給付は国が、現物給付は地方が、との考えをとるのか。(総務大臣・厚労大臣)
4.子ども手当の一部を地方の裁量に任せることやバウチャー方式の検討をする考えはあるのか。(総務大臣・厚労大臣)
5.地域への移譲によって保育の質の低下を招くのではとの懸念にどう対応するのか。(厚労大臣政務官)
Ⅱ.保育制度改革について
1.保育サービスの充実をどのように行うつもりか。(厚労大臣)
2.子育て施策の財源をどこから捻出するつもりか。(厚労大臣)
3.幼保一体化でどういった効果をねらっているのか。(内閣府大臣政務官)
4.認定子ども園を幼保一体化の中でどのように位置づけているのか。(内閣府大臣政務官)
5.認定こども園地方裁量型の声をどのように反映するつもりか。(内閣府大臣政務官)
6.認定子ども園地方裁量型への地方財政措置の実施状況を示していただきたい。(総務大臣政務官)
7.認定こども園地方裁量型への独自の助成が必要ではないか。(厚労大臣)
(認定こども園地方裁量型の質問)
5.認定こども園地方裁量型の声をどのように反映するつもりか。
(内閣府大臣政務官)
この新システム検討会議では、現在各種団体から意見を聴取しておりますが、残念ながらこれまでのところ、認定こども園地方裁量型の方たちの意見を聞く機会が設けられておりません。この地方裁量型の皆さんは、幼稚園、保育園のいずれの認可もない中で、認定こども園の基準をクリアし大変ご苦労をされながら、子どもにとって質の高い教育、保育を実施されています。ぜひともこうした声もお聞きしながら今後のあり方を検討いただきたいと思いますが、どのように反映するつもりかお示しいただきたい。
6.認定子ども園地方裁量型への地方財政措置の実施状況を示していただきたい。
(総務大臣政務官)
この認定こども園地方裁量型には、従来は全く財政的な支援がありませんでしたが、2009年度から新たな財政支援策が制度化され、地方財政措置で対応されることになりました。そこで、この実施状況をお示しいただきたい。
7.認定こども園地方裁量型への独自の助成が必要ではないか。
(厚労大臣)
およそ3,000万円以上が新たに特別交付税で地方裁量型の認定こども園のある自治体に渡ったということで、画期的な第一歩ではあると思いますが、まだまだ他の類型への支援に比べれば規模が小さすぎます。また、既存の制度に対しての地方財政措置なので、実際は、これまで各自治体で取り組んでいた認可外保育施設への支援部分に活かされており、地方裁量型の方たちに対して新規の支援が増えたわけではありません。
やはり、認定こども園として安心・安全な運営ができるように、園庭開放や障害児加算などの独自の対応をしているところにしっかりと助成していくことが必要であると考えますが、厚労大臣のご認識を伺いたいと思います。
2010年04月21日
山口代表vs鳩山総理 党首討論
山口代表=21日 東京都
15時から第3回目の党首討論が行なわれた。
「私は愚かな総理」と言ってしまう鳩山さん。山口代表の追求に終始逃げの答弁。
政治とカネでは、「秘書の国会での参考人招致は解雇したから」。と言い訳。
「資料の提出は出さなくてもいい」などと前回の言葉はうそだった事が明白に。責任を果たそうとの気概なし。
普天間基地問題も「総理就任してから一度も沖縄に行っていない。」沖縄県民を愚弄し続ける。リーダーシップのない総理は国民にとって不幸である。山口代表の爽やかさと明快さが光る党首討論だった。
明日の総務委員会・厚生労働委員会連合審査会で質問をする為、夕方から質問レクを実施。
地方主権法案の保育制度について30分間の質問の予定。11時から11時30分。
国と地方の立場からの保育制度について、総務大臣・厚労大臣に確認してまいりたい。
2010年04月21日
毎日新聞に掲載「軽度外傷性脳損傷」
昨日の厚生労働委員会での質問=21日 東京都
昨日の厚生労働委員会の質問が毎日新聞朝刊に掲載された。委員会質問で壁が破れ、診断基準作成へ研究対象に進むよう応援してまいりたい。
タイトル「軽度外傷性脳損傷:患者に光 厚労省、診断基準作成へ研究」
交通事故などで脳に特異な損傷を負う軽度外傷性脳損傷(MTBI)について、長妻昭厚生労働相は20日の参院厚労委員会で「診断のガイドラインをどう決めていくか検討を進めたい」と述べ、診断基準作成に向けた研究を始める方針を明らかにした。MTBIは国内で認知されておらず、専門家の推定で約30万人いる患者は救済措置もなかったが、政府は方針転換した。
山本博司委員(公明)の質問に答えた。長妻厚労相は「研究が十分ではなかった」と不備を認めた上で「診断基準を決める必要がある。まず医学的知見を蓄積していく。どういう研究が適切か、検討したい」と語った。
MTBI患者は磁気共鳴画像化装置(MRI)などで脳内の損傷が映りにくいため、「MRIなどの画像所見が必要」と定める労災や自賠責保険では救済されず、多くは事故の加害者側に賠償を求めていた。この点に関し長妻厚労相は「画像診断技術の確立も含めて検討したい」と答弁した。また山井和則政務官は「患者団体や専門家の意見を十分にうかがいながら対応を検討していく」と述べた。
労災基準改定を求めている患者団体「軽度外傷性脳損傷友の会」(東京都江東区)の斎藤洋太郎事務局長は「金銭的に困窮している人が多く、一日も早く改定してほしい」と語った。
国内で初めて患者数を調べた湖南病院(茨城県下妻市)の石橋徹医師は「欧米との知識や制度の格差を解消するため、研究班を早く立ち上げてほしい」と話した。【宍戸護】
http://mainichi.jp/select/science/news/20100421ddm012040149000c.html
2010年04月20日
仙台から長男が帰省
家族(妻と長男)=20日 東京都
昨日はめずらしく私の体調がすぐれないと少し妻が仙台の長男に話したら、慌てて東京まで帰ってきた。
元気そうな顔を見て、私も元気を取り戻した。私に代わって連休に予定している北京訪中の買物をしてくれた。家族は本当にありがたい。
2010年04月20日
「脳脊髄液減少症・軽度外傷性脳損傷」から患者を救え!
委員会質問=20日 東京都
朝8時30分から厚生労働部会が開催され、提出法案の党内議論を行なう。
10時から15時過ぎまで厚生労働委員会が開催され、「脳脊髄液減少症・軽度外傷性脳損傷」を中心に40分間、長妻大臣に質問。
制度の狭間で苦しみ悩まれている方々の立場から病気の診断基準・労災などの補償・保険適用の道筋について訴える。
両方の患者会や家族の皆様も傍聴に来られ、真剣に長妻大臣の答弁を聞かれていたのが印象的であった。
患者の皆様の声・要望を国会質問という形で取り上げていただき、本当にありがたい。との喜びの声をいただく。軽度外傷性脳損傷は今日がスタート。脳脊髄液減少症もガイドラインから2012年保険適用まで、まだこれからやるべき課題も多い。
今までの福祉の枠から取り残されているこうした「新しい福祉」に分野について、公明党は、粘り強く解決へ頑張ってまいりたい。
以下質問内容。
Ⅰ.軽度外傷性脳損傷について
1.これまでの政府の対応、認識について伺いたい。
公明党の山本博司でございます。本日は、事故などによって、ある日突然誰にでも起こりうる二つの病気についてお聞きしたいと思います。
はじめに、軽度外傷性脳損傷についてお聞きします。
この軽度外傷性脳損傷は、脳で情報伝達を担う神経線維(軸索)が、交通事故、転倒、スポーツなどで頭部に衝撃を受けて損傷し発症する病気であります。
症状は多様にあり、高次脳機能障害を起こすと、記憶力、理解力、注意・集中力などが低下する。手足の動きや感覚が鈍くなる。また視野が狭くなる。においや味が分からなくなる。耳も聞こえにくくなる。排尿や排便にも支障をきたす。重症では車椅子、寝たきりの生活となる場合もあります。これらの症状は、事故後すぐに現れないことがあり、注意深い経過観察が必要ですが、医師から”むち打ち”や”首のねんざ”などと誤って診断され、適切な治療が受けられず、悩んでいる多くの患者がいらっしゃいます。大部分は、3カ月から1年で回復しますが、1割前後は1年経っても症状が長引き、一生涯、後遺症に苦しむこともあります。外見からではなかなかわからないため、「気のせいではないか」「仮病ではないか」と偏見にさらされている厳しい現状があります。
細川副大臣には、先日、患者の方たちにお会いをいただいて、要望を受けていただいたとのことですが、一刻も早い対策が求められていると思います。
そこで、まず、この軽度外傷性脳損傷について、これまでの政府の対応、どのような認識をお持ちか、確認したいと思います。さらに、労災保険の中で、こうした神経系統の機能に関する障害等級認定基準はどのように扱われているのかお聞きしたいと思います。
2.厚生労働科学研究事業の対象にすべきではないか。
やはり、診断基準を確立することが課題であると思います。医学界においても、軸索損傷に関する論文が出され始めており、本格的な研究体制の整備が急務であると思います。
一説では、国内患者数は推定数十万に上がると推計されています。早期に全国調査を行うとともに、実態の把握や原因の解明、治療のガイドラインを確立するための研究を推進すべきと考えます。厚生労働省では、厚生労働科学研究費の補助金事業がありますが、こうした事業に積極的に取り上げて推進していくべきと考えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。
3.WHOの勧告をどのように受け止めているのか。
さらに、この外傷性脳損傷は「静かなる流行病」として世界的に関心を持たれております。世界保健機関(WHO)は2007年、外傷性脳損傷に関する勧告文を発信しており、その中で「外傷性脳損傷という静かな、そして無視されている流行病に対して、全世界で闘いを組織しよう」と呼び掛けています。WHOによれば、外傷性脳損傷(軽度のほか中等度、重度も含む)は世界で毎年1000万人が罹り、10万人当たりの発生頻度が150~300人ということです。また、WHOは、外傷性脳損傷が2020年には世界第3位の疾患になると予測しています。
また、アメリカの疾病対策センター(CDC)が発表した2003年の外傷性脳損傷に関する連邦議会報告書によれば、米国では毎年150万人が外傷性脳損傷に罹り、5万人が死亡、8万から9万人が後遺障がい者となり、その累計数は米国人口の2%に当たる530万人に達するといわれています。米国では外傷性脳損傷は公衆衛生学上の重要課題として認識され、1996年のクリントン政権時に外傷性脳損傷法が制定されました。
最近では、アフガニスタンやイラクの戦地から帰還した米兵の中に、爆風の衝撃などで軽度外傷性脳損傷患者が多発しているため、オバマ大統領は軽度外傷性脳損傷を軍医療上の重要課題と認めて対策強化策を打ち出しています。
こうした海外での状況を踏まえ、わが国でも対策を強化すべきと考えますが、WHOのこの2007年の勧告を政府としてどのように受け止めているのか、見解を伺いたいと思います。
4.労働喪失の補償という観点から労災基準の等級の見直しが必要ではないか。
日本の医療現場では、CT、MRIなどの画像診断が重視されています。ところが、軽度外傷性脳損傷では軸索と共に近くを走る血管が損傷されて出血が起こらないと、通常のMRIでは脳病変が画像に出ません。出血巣も時間が経つと吸収されてしまします。よって、軽度外傷性脳損傷の軸索損傷が必ず画像に出るとは限らず、現在、軽度外傷性脳損傷の多くの患者が軸索損傷に由来する数々の臨床症状を認めながら、画像診断で「異常なし」とされています。そのために、自賠責や労災で脳の症状と事故との因果関係が認定されず、就労が困難な場合であっても、正当な賠償や補償を受けられずに困窮しているケースが頻発しており、放置できない問題であると思います。
こうした画像診断に出ない患者に対しても、総合的な診断によって障害等級を決定すべきであり、労務困難な場合には、労働喪失の補償という観点から労災保険の障害等級認定基準の等級の適切な見直しが必要であると考えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。
5.画像診断技術などの技術開発の促進支援が必要ではないか。
先ほども申し上げたように、軽度外傷性脳損傷では、CTやMRIの画像に脳病変が出ない場合があります。軸索損傷を抽出する最先端画像診断技術である、「拡散テンソル・トラクトグラフィー」などの研究も進んでいますが、臨床応用は今後の課題であります。
「マンモグラフィ」は乳がんの早期発見に大きな効果を発揮しており、こうした画像診断技術の開発は、わが国が「技術立国」として今後飛躍するには重要な一分野と考えます。政府としても、技術開発の促進支援を積極的に進めるべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。
Ⅱ.脳脊髄液減少症について
1.検査の保険適用を徹底する事務連絡の概要を説明いただきたい。
次に、脳脊髄液減少症についてお聞きします。脳脊髄液減少症は、交通事故や転倒、スポーツ外傷など体への強い衝撃が原因で、脳脊髄液(髄液)が漏れて髄液が減るため、大脳や小脳が下がって神経や血管が引っ張られ、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、倦怠などの症状が出る疾患であります。自立神経失調症やうつ病など他の疾患と誤診されたり、単なる怠慢と扱われ理解されない事例もあり、患者皆さんにとっては、一日も早い診断・治療法の確立が求められております。そうした中、髄液漏れが起きている部分に患者自身の血液を注入し、漏れを防ぐ「ブラッドパッチ療法」で、むち打ちの症状が改善したという報告が相次ぎ、関心を集めています。
この脳脊髄液減少症について、4月12日に長妻大臣は、患者団体の方とお会いし、「ブラッドパッチ療法」の次期診療報酬改定での保険適用に前向きな姿勢を示したとのことであります。また、厚生労働省は4月13日、脳脊髄液減少症の疑いがある患者の検査について、保険診療の対象とするよう周知徹底する通知を、全国の自治体に出しました。そこで、まず、この事務連絡の概要についてご説明いただきたい。
2.研究事業の今後の見通しはどのようになっているのか。
これまで、地域によってばらつきがあるという現状がありましたので「当たり前のことが当たり前になっただけ」との指摘もあります。検査の保険適用について周知徹底されるようお願いしたいと思います。
この脳脊髄液減少症については、2007年度より厚生労働省の厚生労働科学研究事業の一つとして「脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究班」が設置され、髄液漏れと症状との因果関係を明らかにし、診断基準の作成や治療法の確立、さらに誰が見ても納得できる診療指針であるガイドラインの作成を目的に研究事業が進められてきました。
ところが、残念ながら当初予定の3年間の研究期間内では、科学的な根拠にもとづく診断基準を作るために必要な数の症例を得るには至りませんでした。そこで、症例100例を目指して今年度も研究を継続して行うこととなり、100例が集まった時点でガイドラインを作成すると理解していますが、今後の研究事業の見通しについてどのようになっているのかご説明いただきたいと思います。
3.ブラッドパッチ療法を保険適用にすべきではないか。
今年度に脳脊髄液減少症の診断基準の作成、来年度に「ブラッドパッチ療法」の診療ガイドライン、さらに2012年度に保険適用という当初描いていたスケジュールとなれば、大臣が示された次期診療報酬の改定に間に合うと思いますので、ぜひとも強力に推進していただきたいと思います。
公明党は、患者団体からの要請を受け、2002年から脳脊髄液減少症の問題に取り組んできました。当時、公明党以外どの政党も取りあわなかった問題でした。2004年3月には、遠山清彦参院議員(現在衆院議員)が、参院厚生労働委員会で研究推進などを要請し、古屋範子衆院議員もブラッドパッチ療法の研究と保険適用を求める質問主意書を提出しました。2004年12月には浜四津敏子代表代行らが、「脳脊髄液減少症患者支援の会」の代表とともに当時の西博義厚労副大臣に、10万人を超える署名簿を添えて、治療法確立やブラッドパッチ療法への保険適用などを要請しました。2006年3月には渡辺孝男参院議員の質問が契機となって、翌2007年から研究班が設置されました。
さらに、都道府県議会などの地方議会でも患者団体と連携し、行政にも積極的に働き掛け、2007年には全都道府県において、「脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書」が採択されました。また、現在は42府県の公式ホームページで脳脊髄液減少症の治療可能病院が公開されるなど対策が進んでいます。
このように、わが党は8年前からこの課題に取り組んでまいりましたが、こうした課題は、本来ならば超党派で取り組むべきと考えます。
いよいよブラッドパッチ療法の保険適用に向けて具体的な段階になってきたと思います。着実に前へ進むように大臣のご尽力をお願いしたいと思いますが、この点について認識を伺いたいと思います。